【体験談】脳性まひの子を育てるママの葛藤と乗り越え方|利用できる制度・相談先も解説
「どうして、うちの子だけ…」
「この子の将来はどうなるんだろう…」
脳性まひの子どもを育てる毎日は、先の見えない不安や、周りと比べてしまう罪悪感との闘いかもしれません。私自身、息子に脳性まひの診断が下された時、目の前が真っ暗になりました。
この記事で分かること
この記事では、脳性まひの息子を育てる私のリアルな体験談を交えながら、母親が抱える葛藤の正体と具体的な乗り越え方、そして子育てを支える公的な支援制度や相談先まで、網羅的に解説します。
- 障害児育児で母親が抱えがちな葛藤と、その向き合い方
- 知っておくべき「療育」の基礎知識と具体的な支援サービス
- 【保存版】療育手帳や産科医療補償制度など、お金と制度の知識
- 一人で抱え込まないための具体的な相談先リスト
この記事を読み終える頃には、心のモヤモヤが少し晴れ、「明日から何をすれば良いか」が見えているはずです。どうか一人で抱え込まず、一緒に歩んでいきましょう。
【私の体験談】障害児育児で感じた母親としての葛藤
障害児育児は、喜びも大きい反面、言葉にできない葛藤との闘いでもあります。私が特に強く感じたのは、以下の3つの感情でした。
1. 「全部やらなきゃ」完璧を求めすぎて疲弊する自分
「この子のために、できることは全部やらなきゃ」。診断当初の私は、使命感に燃えていました。療育、リハビリ、情報収集…。スケジュール帳は真っ黒。しかし、その頑張りが裏目に出て、心と体を追い詰めてしまいました。
完璧を目指すあまり、できない自分を責め、常に焦りを感じる…。そんな悪循環に陥っていました。
2. 他の子と比べてしまう罪悪感
療育センターや公園で、同じくらいの年齢の子どもが元気に走り回る姿を見るたび、胸が締め付けられました。「どうしてうちの子はまだ歩けないの?」「他のママは上手にやっているのに…」。
頭では「比べても意味がない」と分かっていても、自己否定の感情が波のように押し寄せ、心が擦り減っていきました。
3. 先の見えない未来への不安
子どもの将来を考えると、不安で眠れない夜が何度もありました。
- この先、学校や就職はどうなるんだろう?
- 私たちが年老いたら、この子はどうやって生活していくの?
- 医療費や支援サービスの費用は、払い続けられるだろうか?
先の見えない道を手探りで進むような感覚は、常に私に重くのしかかっていました。
葛藤を乗り越えるために|心を軽くする3つのステップ
そんな葛藤の中でもがいた私が、少しずつ前を向けるようになった実践的な方法を3つご紹介します。
Step1. 「70点育児」で完璧主義を手放す
ある日、カウンセラーに言われた「100点じゃなくていい。70点で十分ですよ」という言葉に救われました。それからは、「今日はこれができたからOK」と自分を許すように。すべてを完璧にこなすのではなく、子どもと自分のペースを大切にすることが、心の余裕を生み出しました。
Step2. 同じ境遇のママと繋がり、孤独を和らげる
孤独は、不安を増幅させます。私が救われたのは、地域の「親の会」でした。「分かる!うちもそうだよ」と共感し合えるだけで、心が軽くなるのを感じました。今はSNSなどでも簡単につながりを見つけられます。安心して本音を話せる場所は、何よりの心の支えになります。
Step3. 自分のための時間を作る(意識的に!)
「母親なんだから」と自分を後回しにしがちですが、ママの笑顔が子どもの元気の源です。私は週に一度、30分だけでも好きな音楽を聴きながら散歩する時間を作りました。自治体によっては、一時的に子どもを預かってくれる「レスパイトケア」などのサービスもあります。意識的に心と体をリセットする時間を持つことが、本当に大切です。
【保存版】知っておきたい療育・支援制度の基礎知識
不安を和らげるためには、「知る」ことが一番の武器になります。ここでは、私が実際に利用したり調べたりした、特に重要な制度を3つ、体験談を交えて解説します。
1. 療育の第一歩「児童発達支援」
児童発達支援とは、障害のある未就学児(0〜6歳)が、身近な地域で専門的な支援を受けるための通所サービスです。理学療法(PT)や作業療法(OT)などのリハビリや、日常生活の自立支援など、子どもの発達段階に合わせたプログラムが提供されます。
【私の体験談】
息子が2歳の時から週2回、児童発達支援に通っています。最初は場所見知りをして泣いてばかりでしたが、専門の先生方が根気強く関わってくださり、今では笑顔で通えるようになりました。親にとっても、子どもの成長を相談できる貴重な場所になっています。事業所によって特色が違うので、いくつか見学して、お子さんに合う場所を見つけるのがおすすめです。
利用には「通所受給者証」が必要です。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみましょう。
詳しくは、厚生労働省の公式サイトもご確認ください。
2. 各種サービスに繋がる「療育手帳」
療育手帳とは、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。障害の程度によって区分が分かれており、様々な福祉サービスを受けるために必要となる場合があります。脳性まひの場合でも、知的発達の状況に応じて対象となることがあります。
【私の体験談】
息子の場合は3歳の時に申請し、手帳を取得しました。申請には児童相談所での面談や発達検査がありました。手帳があることで、特別児童扶養手当の申請がスムーズになったり、公共交通機関や施設の割引を受けられたりと、経済的なメリットを実感しています。手帳を持つことに抵抗がある方もいるかもしれませんが、私は「使えるお守り」だと捉えています。
申請窓口や制度の詳細は自治体によって異なります。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で「療育手帳について相談したい」と伝えてみてください。
3. 出産時のトラブルが原因の場合「産科医療補償制度」
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さんとそのご家族の経済的負担を補償する制度です。全ての分娩機関が加入しており、所定の要件を満たす場合に補償金が支払われます。
【私の体験談】
息子の脳性まひの原因が出産時のトラブルにある可能性を医師から示唆され、この制度に申請しました。診断書や様々な書類の準備は大変でしたが、結果として補償の対象となり、一時金と分割金を受け取ることができました。これにより、将来の医療費や介護費用への不安が大きく軽減されました。もし、お子さんの脳性まひの原因が出産時かもしれないと感じたら、諦めずに一度相談してみることを強くお勧めします。
申請条件や方法は複雑なため、まずは公式サイトを確認するか、出産した分娩機関、または専門の相談窓口に問い合わせてみましょう。
具体的な相談先・支援機関リスト
「誰に」「どこに」相談すれば良いか分からない、という方のために、具体的な相談先をリストアップしました。一つの場所で解決しようとせず、複数の窓口を頼るのがポイントです。
- お住まいの市区町村の障害福祉窓口:すべての基本となる場所。制度の案内や申請を受け付けています。
- 保健センター:保健師さんが親身に相談に乗ってくれます。乳幼児健診の際に相談するのも良いでしょう。
- かかりつけの小児科・療育センターの医師やソーシャルワーカー:医療的な視点から、必要な支援や制度についてアドバイスをくれます。
- 地域の親の会・オンラインコミュニティ:同じ境遇の親同士で、リアルな情報交換ができます。精神的な支えにもなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 周囲からの無理解な言葉に傷つきます。どうすればいいですか?
A1. とても辛いですよね。悪気がない言葉ほど、心に刺さるものです。すべての人に理解してもらうのは難しいと割り切り、「この人には話しても伝わらないな」と思ったら、心の中でそっとシャッターを下ろすことも大切です。あなたの頑張りを分かってくれる人との時間を大切にしてください。
Q2. 子どもの日々の成長を、素直に喜べない時があります。
A2. そんな日もあります。自分を責めないでください。周りの子の成長スピードと比べず、昨日より今日、ほんの少しでもできたこと、笑ってくれたことなど、あなたのお子さん自身の「小さな成長」に目を向けてみましょう。写真や動画で記録しておくと、後で見返した時に成長を実感できて、励みになりますよ。
Q3. 支援制度が複雑で、どこから手をつければいいか分かりません。
A3. まずは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に「脳性まひの子どもがいて、利用できる制度について知りたい」と電話一本するところから始めてみましょう。一度にすべてを理解しようとせず、一つずつで大丈夫です。担当者が丁寧に教えてくれますし、そこから次のステップが見えてきます。
まとめ:明日への小さな一歩を踏み出そう
この記事では、脳性まひの子を育てる母親のリアルな葛藤と、それを乗り越えるための心の持ち方、そして具体的な支援制度について、私の体験を交えてお伝えしました。
たくさんの情報に圧倒されたかもしれません。でも、すべてを一度にやろうとしなくて大丈夫です。大切なのは、「完璧を目指さないこと」そして「頼れる先を知っておくこと」です。
まずは今日、この記事で知った相談先の電話番号をメモするところからでも構いません。その小さな一歩が、必ずあなたとお子さんの明日を、少しずつ明るく照らしてくれるはずです。
あなたの愛情と頑張りは、何よりも尊い力です。どうか、ご自身のことも大切にしてくださいね。

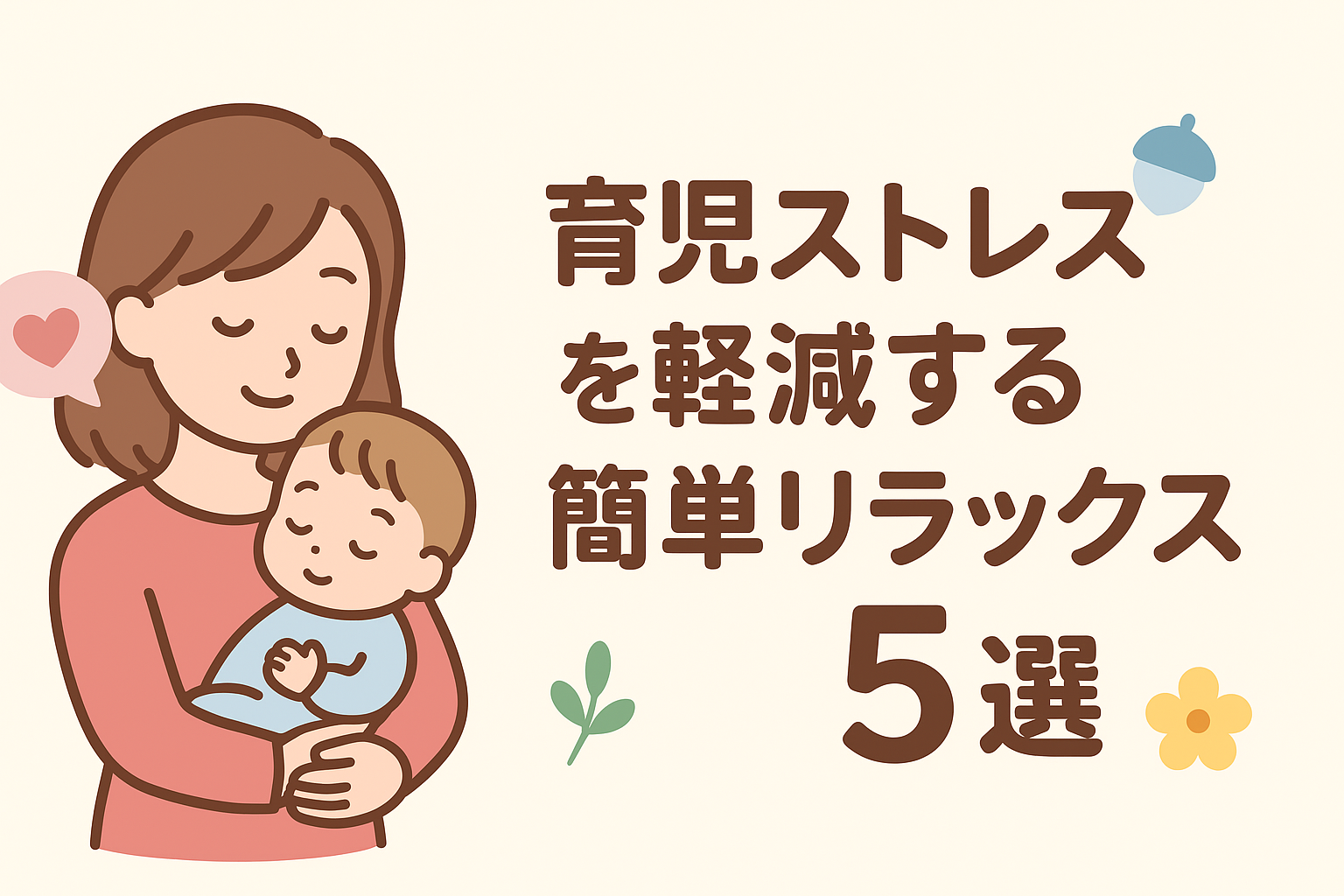
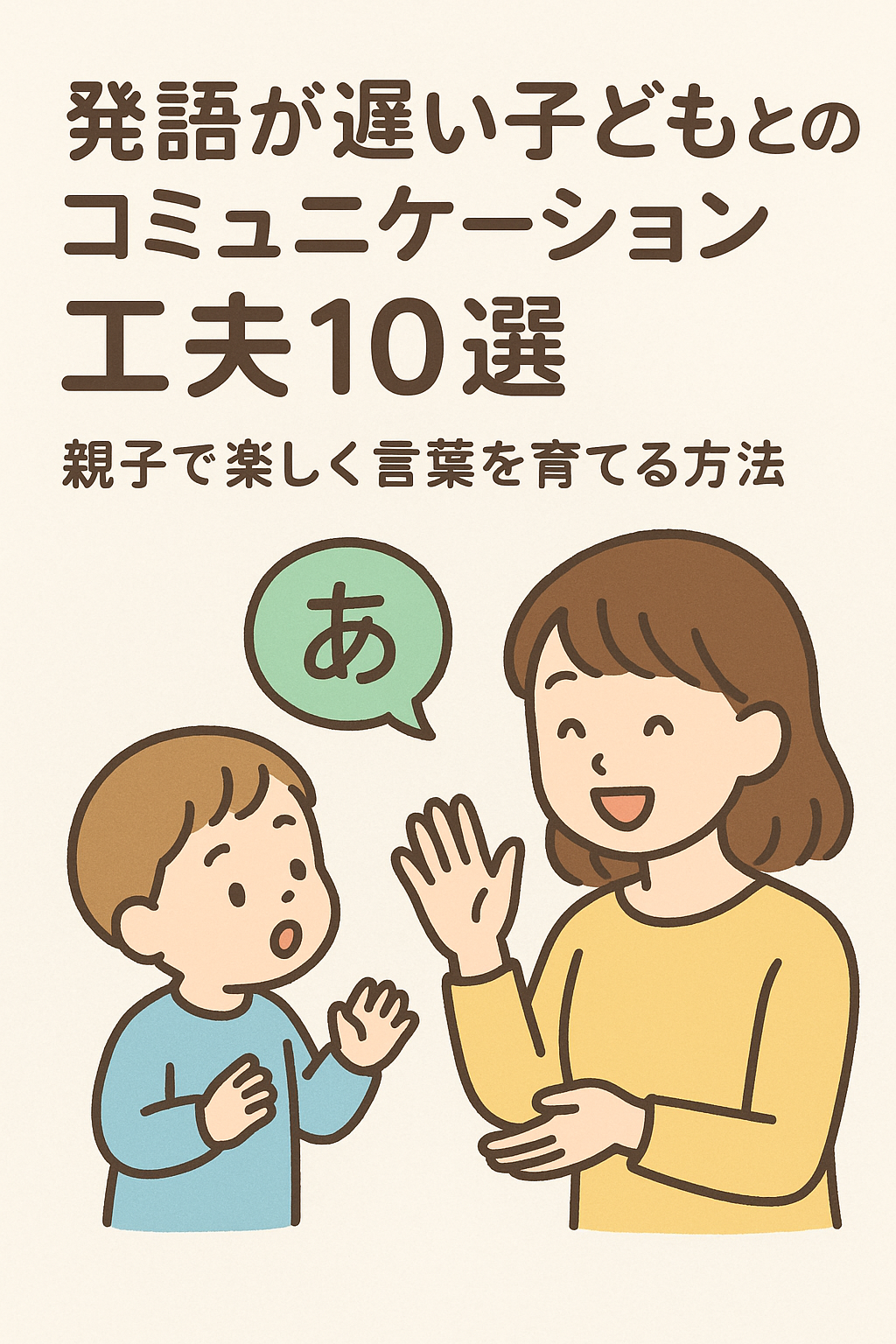
コメント