【専門家も推奨】療育ママの”見えない疲れ”を軽くする5つのセルフケア法
🌼この記事で分かること:結論ファースト
「日々のリハビリ、本当に意味あるのかな…」「周りの子と比べて落ち込んでしまう…」
脳性まひの子どもを育てる毎日は、喜びと同じくらい、見えない不安や心労が積み重なりますよね。
私自身、息子のケアに追われ、自分のことは後回し。気づけば笑顔を忘れ、自己嫌悪に陥る日々の繰り返しでした。
この記事では、そんな療育を頑張るママにこそ知ってほしい、専門家の視点を取り入れた具体的なストレス解消法を、私の体験談を交えて解説します。読み終える頃には、日々の生活で実践できるセルフケアの方法から、一人で抱え込まないために利用できる公的なサポートまで分かります。
💭 なぜ?療育ママが抱える特有のストレスとその背景
一般的な育児ストレスに加え、療育中のママは特有の悩みを抱えがちです。
- 終わりが見えない不安:「この先どうなるんだろう」という長期的な不安との闘い。
- 24時間の緊張感:医療的ケアや急な体調変化への備えなど、気が休まる時がない。
- 社会からの孤立感:地域の集まりに参加しづらかったり、悩みを気軽に話せる相手がいなかったりする。
これらのストレスは、ママ一人の責任ではありません。こども家庭庁も障害児支援の重要性を説いており、親へのサポート体制も整備されつつあります。まずは自分を責めず、正しい知識で対処していくことが大切です。
🌟 専門家の視点を取り入れたストレス解消法5選
1️⃣ 理学療法士も推奨!「体をゆるめる」コンディショニング 🤸♀️
解説:子どもの抱っこや移乗介助で、ママの体は知らず知らずのうちに凝り固まっています。体の緊張は心の緊張に直結します。特別な運動ではなく、まずは「ゆるめる」ことを意識しましょう。
- 肩甲骨はがし:タオルを両手で持ち、背中側で上下に動かす。洗濯物を干す「ついで」にできます。
- 股関節ストレッチ:床に座り、足の裏を合わせて膝を優しく揺らす。子どもの横で遊んでいる時にできます。
💡 私の体験談
公式の情報では「適度な運動を」と書かれていますが、その時間すらないのが現実…。そこで、息子の担当の理学療法士(PT)さんに「ママが自分の体をケアする方法」を聞いてみました。教えてもらったのは、介助で一番負担のかかる肩甲骨と股関節を「ながら」でほぐす方法。これを続けてから、慢性的な肩こりや腰痛がずいぶん楽になり、心にも少し余裕が生まれました。
2️⃣ 臨床心理士も使う「マインドフルネス呼吸法」 🌬️
解説:「今、ここ」に意識を集中させる呼吸法は、将来への不安から心を解き放つのに効果的です。医療やカウンセリングの現場でも用いられる、科学的根拠のあるリラックス法です。
- 椅子に座るか、楽な姿勢をとる
- 鼻から4秒かけてゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる
- 口から6〜8秒かけて、細く長く息を吐ききる
- これを1分間繰り返す
💡 私の体験談
子どもの体調が急変した時や、リハビリがうまくいかず焦る時、頭が真っ白になっていました。そんな時、この呼吸法を1分間だけ実践すると、高ぶった感情がスーッと落ち着き、冷静に対応できるようになったんです。「怒鳴る前に一呼吸」どころか、「パニックになる前に一呼吸」おけるお守りのような習慣です。
3️⃣ SNS疲れから脱却!「ピアサポート」と繋がる 🤝
解説:SNSで他の子の成長を見て落ち込むのは、情報収集の方法が合っていないからかもしれません。同じ悩みや境遇を分かち合える仲間と繋がる「ピアサポート」は、何よりの心の支えになります。
- お住まいの自治体の「障害児(者)親の会」を探す
- SNSで同じ病気の子を持つ親のコミュニティ(鍵付きアカウントなど)を探す
💡 私の体験談
「デジタルデトックス」も大事ですが、私は情報を遮断するより「繋がる相手を選ぶ」ことにしました。市の福祉課で紹介してもらった親の会に参加し、「うちもそうだよ!」と言ってもらえた時、涙が出るほど安心しました。有益な制度の情報を交換したり、ただ愚痴を言い合ったりできる仲間は、最高の処方箋です。
4️⃣ 罪悪感は不要!公的サービスで「何もしない時間」を作る ☕
解説:ママの休息は、子どもの健やかな発達のためにも不可欠です。障害児支援サービスは、そのために用意されています。専門スタッフに子どもを預け、心と体を休ませる時間を持つことは、親の権利です。
- 短期入所(ショートステイ):数時間〜数日間、施設に子どもを預けられるサービス。
- 居宅介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅に来て、入浴や食事の介助をしてくれるサービス。
- 移動支援:通院や外出の際に、ヘルパーが付き添ってくれるサービス。
💡 私の体験談
「子どもを預けて休むなんて…」と最初は強い罪悪感がありました。でも、相談支援専門員の方に「ママが倒れる前に、使えるものは全部使いましょう」と背中を押され、月1回、半日だけショートステイを利用。たった数時間、一人でカフェに行くだけで、驚くほど心が軽くなり、帰宅後、新鮮な気持ちで子どもに接することができました。「詳しくは、お住まいの自治体の福祉窓口や相談支援事業所にご確認ください」と案内されていますが、まずは電話一本からで大丈夫です。
5️⃣ 小さな「できた」を記録する1行日記 📝
解説:できないことや不安なことばかりに目が行きがちですが、意識的に「できたこと」「嬉しかったこと」に目を向けることで、自己肯定感を高めることができます。これは認知行動療法でも使われるテクニックの一つです。
- 「今日、リハビリで〇〇ができた」
- 「訪問看護師さんと笑い合えた」
- 「天気が良くて気持ちよかった」
💡 私の体験談
寝る前に、スマホのメモ帳に今日の「よかったこと」を1行だけ書く。これだけです。見返してみると、「自分、意外と頑張ってるな」「つらいことばかりじゃなかったな」と客観的に自分を認められるようになります。漠然とした不安が、具体的な「できた」の積み重ねに変わっていく感覚です。
✨ まとめ:ママの笑顔がお子さんにとって一番の療育です
療育ママのストレスは、決して「我慢」で解決するものではありません。
専門的な知識を取り入れ、利用できるサービスを上手に活用しながら、「自分をケアする」視点を持つことが大切です。
今回ご紹介した5つの方法の中から、どれか1つでも構いません。「これならできそう」と思うものから、ぜひ試してみてください。
ママが心から笑顔でいられる時間が増えることが、お子さんにとって最高の安心と発達の土台になります。
❓ よくある質問(Q&A)
Q1. 公的なサービスを利用することに罪悪感があります。
➡️ A1. 気持ちはとてもよく分かります。ですが、親の休息は子どものためでもあります。共倒れを防ぎ、長く続く療育生活を乗り切るための「戦略的休息」と考えてみてください。まずは見学や数時間の利用から始めるのもおすすめです。
Q2. どこに相談すれば良いか分かりません。
➡️ A2. まずは、お住まいの市区町村の「福祉課(障害福祉担当)」や「保健センター」に電話してみるのが第一歩です。また、療育手帳の申請時などにお世話になる「相談支援事業所」の相談支援専門員さんは、使えるサービスを一緒に探してくれる心強い味方です。
Q3. 夫や家族に大変さを理解してもらえません。
➡️ A3. 「言わなくても分かってほしい」は、残念ながら難しいことが多いです。感情的に訴えるのではなく、「市の相談員さんから、こういうサービスを使って休息を取るように言われた」など、第三者や公的な情報を交えて話すと、冷静に聞いてもらいやすくなる場合があります。
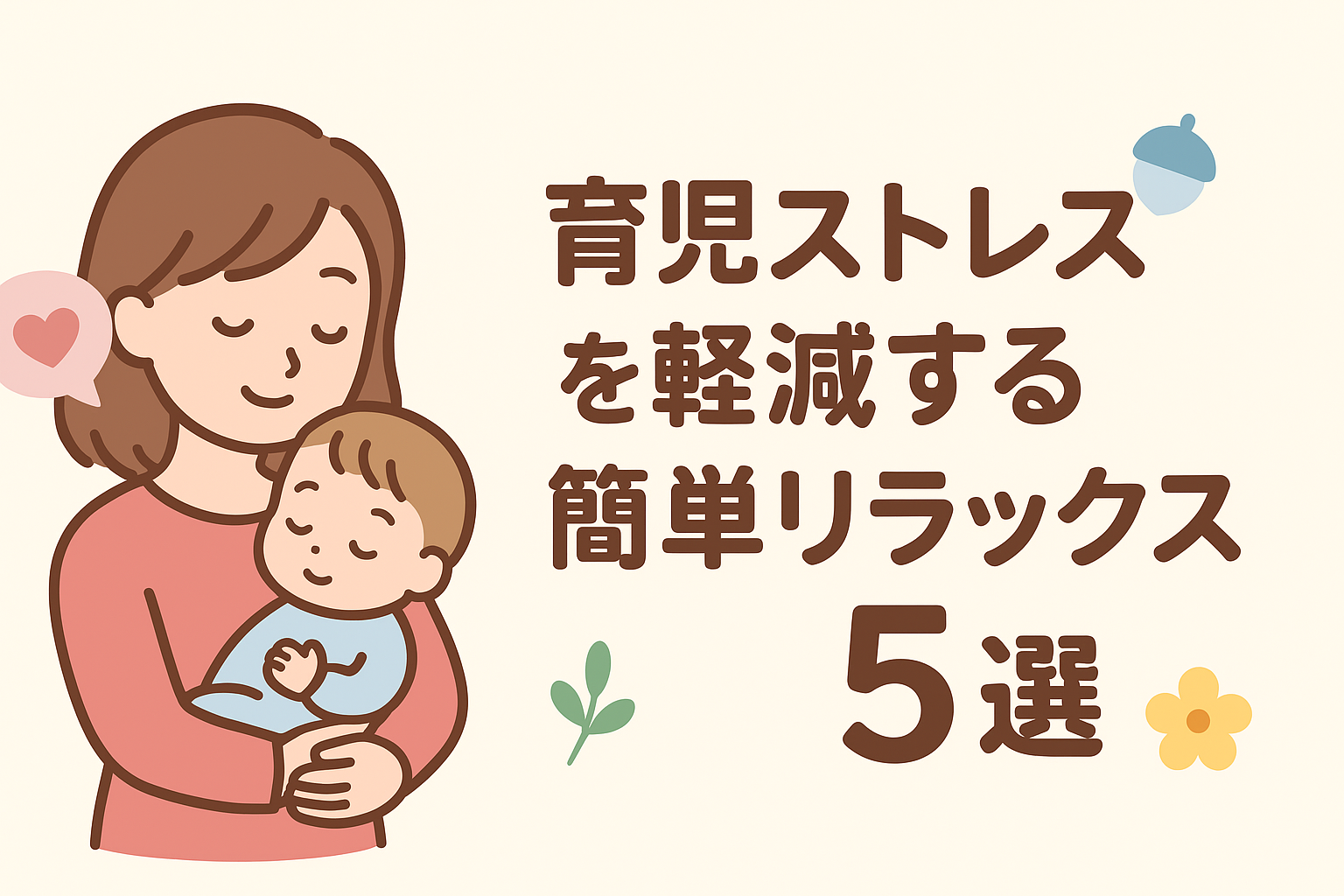
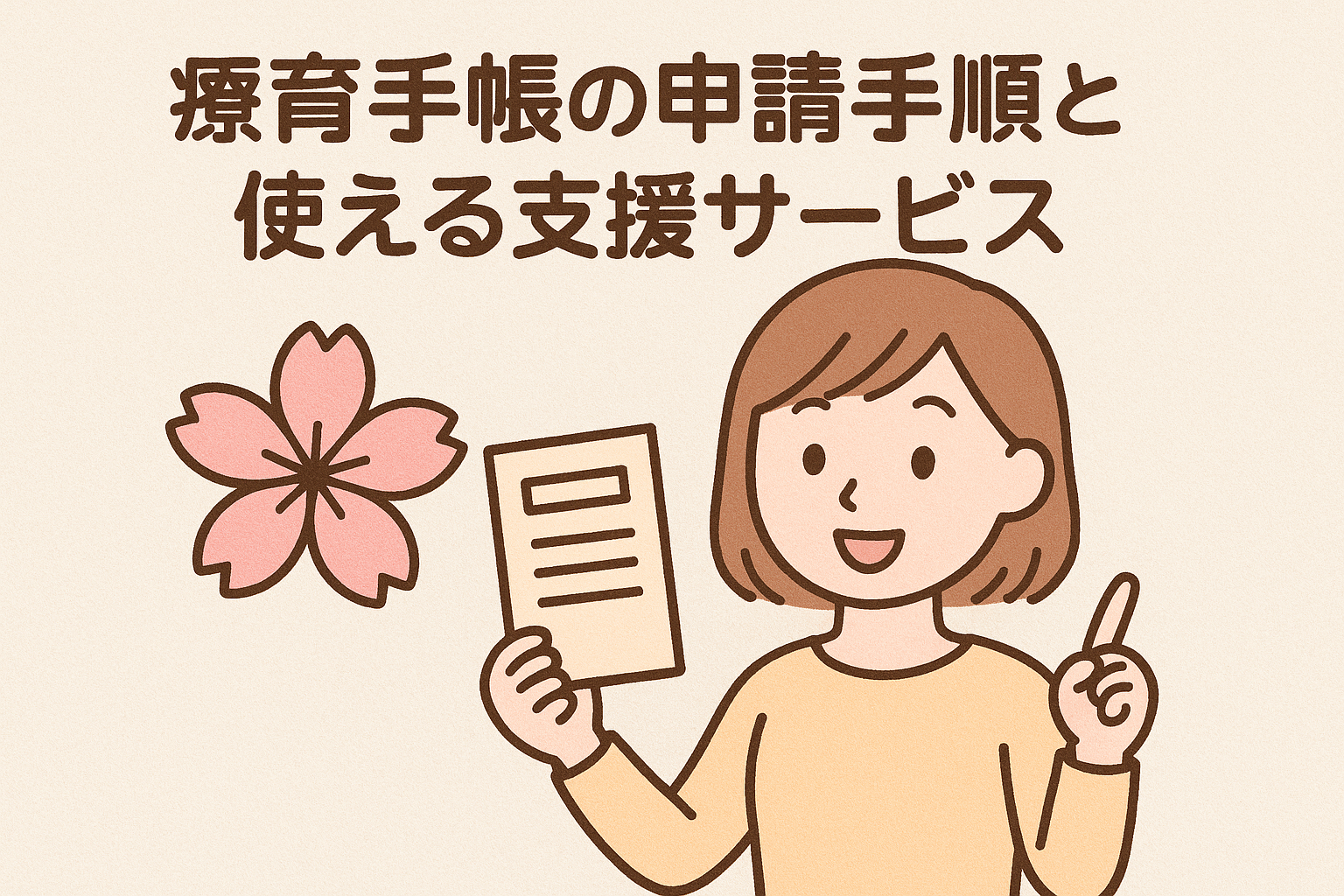

コメント