はじめに🌱
障害のある子どもを育てる上で、親として一番不安に感じるのが
「この子に必要な支援は本当に受けられるの?」
ということではないでしょうか。
特に、言葉がまだ発達していない幼児期は、親が「気づき、調べ、動く」ことがとても重要です。
しかし福祉制度は複雑で、
- どんな支援があるのか
- どう申請すればいいのか
知らないまま過ごしてしまう方も多いのが現実です。
そこでこの記事では、私自身の体験も踏まえ、
✅ 重度障害児向けの福祉サービス一覧
✅ 療育手帳・身体障害者手帳の申請方法
✅ 医療的ケア児への特別支援制度
✅ 支援を受けるときの注意点
などをわかりやすく解説します。
1. 療育手帳・身体障害者手帳とは? まずはここから理解しよう📋
療育手帳とは?
知的障害がある場合に交付される「療育手帳」は、障害者福祉サービスを受けるための基本的な手帳です。
自治体によって名称や判定基準は異なりますが、主に
- A(重度)
- B(中・軽度)
の区分があります。
この手帳を持つことで、
- 医療費助成
- 介護サービスの利用(通所支援など)
- 公共交通機関の割引
- 税金の優遇
などのさまざまな支援が受けられます。
身体障害者手帳とは?
身体障害(肢体不自由、視覚障害、聴覚障害など)がある場合は、別に「身体障害者手帳」を申請します。
知的障害と身体障害が両方ある場合は、それぞれの手帳を取得できます。
2. 移動支援と通所支援とは? 具体的なサービス内容🚗🏠
移動支援(地域生活支援事業)
移動支援は、
- 病院や療育施設への付き添い
- 公園や買い物の外出サポート
- 家庭以外の人と交流する時間の確保
など、外出のための支援です。
支援員が一対一で付き添い、親の負担を軽減してくれます。
私の体験では、初めて移動支援を利用したとき、親切な対応に涙が出そうになりました。
子どもも外出が楽しみになり、良い刺激となっています😊
通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援)
通所支援は、3歳から小学校入学前の子どもが利用できます。
提供されるサービスは、
- 集団・個別療育プログラム
- 理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語療法(ST)
- 日常生活の自立支援
特に医療的ケアが必要な場合は、「医療型児童発達支援」という専門施設も紹介されます。
3. 医療的ケア児支援とは?専門の支援が必要な場合⚕️
医療的ケア児とは、
- たんの吸引
- 経管栄養(胃ろう)
などを日常的に行う必要がある子どものことを指します。
こうした子どもは、通常の保育園や通所施設では対応が難しく、
- 看護師常駐の専門保育施設の利用
- 訪問看護の活用
- 医療的ケア児支援センターの相談
など、特別な支援が必要です。
もし市区町村の窓口で「対応が難しい」と言われたら、
県や広域支援センターに直接問い合わせてみてください。
情報が届いていないだけ、ということも少なくありません。
4. 療育センター活用のすすめ🏥 〜親子の支え合いの場〜
私にとって大きな支えとなったのが、地域の療育センターでした。
- 発達検査の実施
- 専門スタッフによる個別療育
- 保護者同士の交流・相談
があり、「私たちはひとりじゃない」と感じられました。
5. 支援制度を使うことへの心理的ハードルを乗り越える🤝
支援を受けることに
- 「申し訳ない」
- 「甘えなのでは」
と感じる親御さんも多いです。
でも、制度は「困っている人のためにある」ことを忘れないでください。
支援を利用することで、親の心に余裕が生まれ、子どもにとっても安心できる環境が作れます。
【よくある質問(FAQ)】❓
Q1. 療育手帳の申請方法は?
A. 医師の診断書をもとに自治体の福祉課や保健センターで申請します。自治体ごとに必要書類や流れが異なるため、事前に確認が必要です。
Q2. 医療的ケア児向けの施設はどう探せばいい?
A. まずは市区町村の障害福祉窓口に相談しましょう。専門的な施設の情報提供や紹介を受けられます。
Q3. 支援を受ける際の費用は?
A. 多くのサービスは無料または低額ですが、自治体により異なります。
Q4. 福祉サービスを利用しながら働きたい場合は?
A. 障害児を育てる親向けの就労支援もあります。自治体やハローワークに相談してみましょう。
まとめ🌟
重度障害児の育児は、たくさんの不安や手間があります。
でも、適切な福祉支援や療育サービスを利用することで、
- 子どもに合った環境を整えられる
- 親の心身の負担を軽減できる
という大きなメリットがあります。
まずは「情報収集」と「相談」から始めてみてくださいね。
✨ この記事が、重度障害児の子育てに悩む親御さんの一助になれば幸いです。


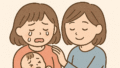
コメント