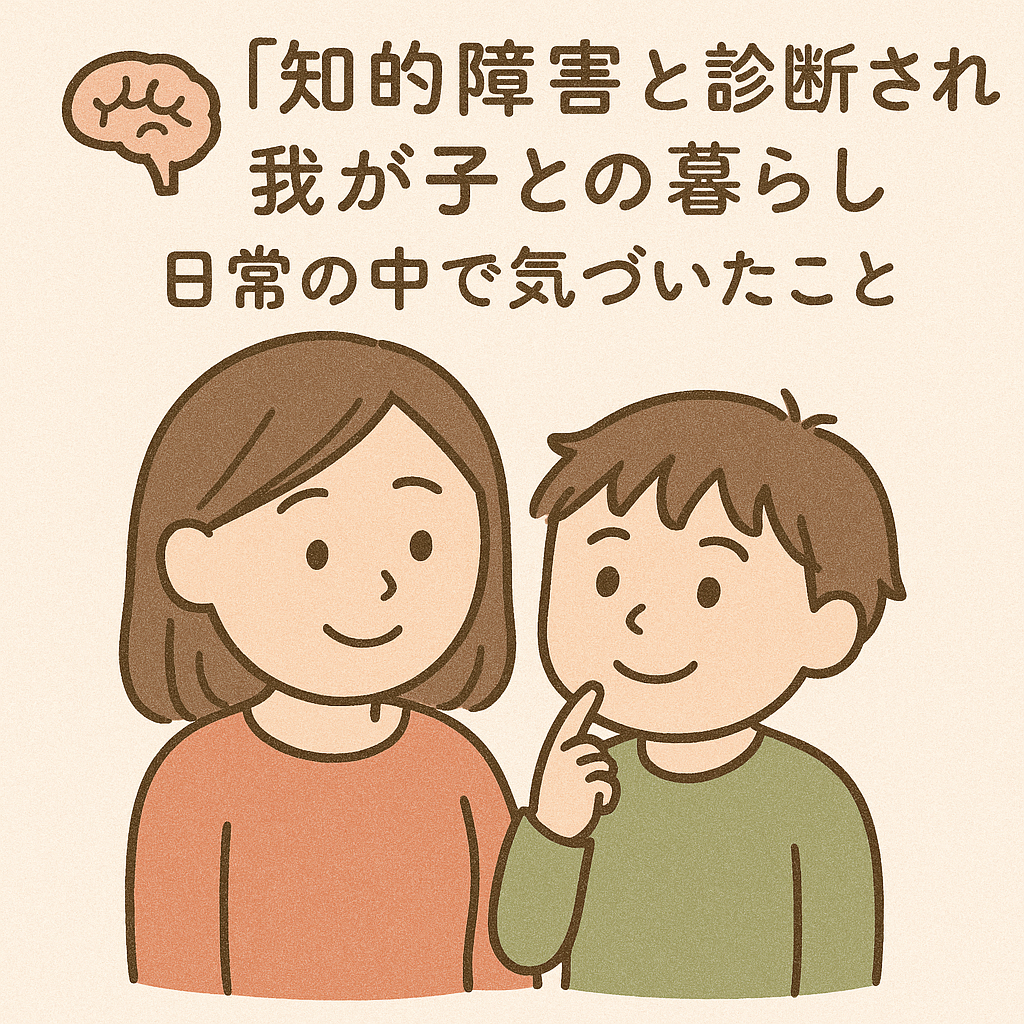
🌀 発達検査を受けるまでの葛藤と、その先に見えた景色
🌱 はじめの違和感
「なんとなく、同じ月齢の子と違うかもしれない――」
そう感じたのは、息子が1歳半を過ぎた頃でした。
- 言葉がなかなか出ない
- 指差しやアイコンタクトが少ない
- 名前を呼んでも振り向かないことが多い
最初は「きっと個性だよね😊」と自分に言い聞かせていました。
しかし、公園や児童館で同じ年の子が次々と単語を話し始め、おもちゃを上手に使って遊んでいるのを見るたびに、胸の奥でチクリとした不安が疼き始めました。
💭 迷いと葛藤 ~発達検査に踏み切れなかった理由~
発達検査を受けようと思っても、すぐには動けませんでした。
なぜなら…
- 「ラベルを貼りたくない」強い気持ち
- 「うちの子は大丈夫」と信じたい願望
- 周囲からの「そのうち話すようになるよ」という言葉
特に「大丈夫だよ」という言葉は、優しさの裏に不安を抱えた私を立ち止まらせる力がありました。
🏥 発達検査の受診と診断結果
迷いに迷いながら、市の保健センターに相談し、児童発達支援センターを紹介してもらいました。
検査は息子が2歳3か月のときに受けました。
発達検査とは?
発達検査は、子どもの言語能力や運動機能、社会性など発達の状態を専門家が評価する検査です。
主に「発達障害の早期発見と適切な支援」を目的に行われます。
息子の検査結果は――
「知的障害の可能性があります」でした。
涙は出ませんでした。
心の中でぐるぐるしていた不安が、**“形”**になって目の前に現れたことで、むしろ少し安心したのを覚えています。
📝 診断名がついて変わったこと
「診断名」と聞くと、多くの人はネガティブなイメージを抱くかもしれません。
しかし、我が家にとっては、それが新たな出発点になりました✨
🌟 診断後の変化リスト
- ✅ 療育センターの利用が可能になった
- ✅ 発達支援の専門家から息子の特性について具体的な説明を受けた
- ✅ 福祉制度(療育手帳など)の申請がスムーズに進められた
- ✅ 保育園や行政との連携が取りやすくなった
何よりも――
「どうしてこの子はこうなのか?」という疑問が
「こういう特性があるからなんだ」へと変わり、心がとても軽くなりました。
🌱 ゆっくり育つけれど、確かに成長している姿
3歳になった今も、はっきりとした言葉はまだ少なく、お友達との会話もほとんどありません。
しかし、確実に小さな進歩があります。
✅ 自分で靴を履こうとする
✅ 名前を呼ぶと振り向く
✅ 「かぁか」と笑顔で呼んでくれる
かつては「できないこと」にばかり目がいっていましたが、今では**「昨日できなかったことが今日できた」**その瞬間の価値を深く感じています。
🤝 わが家のコミュニケーション術
息子は言葉が少ないため、様々な工夫をしています。
- 🖼 写真カードを使い、「お茶」「おもちゃ」などの意思表示を促す
- 🤲 手を引いて指示行動を尊重する
- 😊 表情や声のトーン、ジェスチャーを丁寧に読み取る
こうして、「言葉がない=伝えられない」ではないことを日々実感しています。
💌 周囲との関わりと私の心の持ち方
障害児育児は、理解されにくいことも多くあります。
ですが、保育園の先生や療育の専門家が息子の特性を理解し、日常での関わり方を共有してくれることは何より心強いです。
- 🌟 無理に“普通”に合わせようとしない
- 🌟 「うちのペース」で進むことを大切にする
- 🌟 成長の形はひとつではない
こう思えるようになったのは、診断を受けたからこそです。
📌 発達検査を受けるには?
もし、「もしかして?」と思ったら、まずは市区町村の保健センターや児童相談所、発達支援センターに問い合わせてみましょう。
多くの自治体で、無料で相談できる窓口があります。
▼ 相談時に伝えるポイント
- 気になる行動や発達の遅れの具体例
- いつから感じているか
- 周囲の反応や支援の有無
専門家が状況を聞き、必要に応じて発達検査の案内をしてくれます。
❓【よくある質問(FAQ)】❓
Q1: 発達検査はどこで受けられますか?
➡️ 市区町村の保健センター、児童相談所、児童発達支援センターで受けられます。
まずは電話や窓口で相談してみてください。
Q2: 発達検査は費用がかかりますか?
➡️ 多くの自治体では無料または低額で受けられます。
詳細はお住まいの自治体にお問い合わせを。
Q3: 発達検査の結果に納得できない場合は?
➡️ セカンドオピニオンを求めたり、別の専門機関で再検査を受けることも可能です。
疑問があれば、遠慮なく相談してください。
Q4: 療育センターって何をするところ?
➡️ 発達に遅れや課題のある子どもと家族を支援する施設です。
理学療法、作業療法、言語療法など専門スタッフによる療育プログラムが受けられます。
Q5: 療育手帳はどうやって申請するの?
➡️ 診断書を持って自治体の福祉窓口で申請します。
申請方法や条件は自治体によって異なるので事前に確認を。
Q6: 発達障害の子どもとどう接したらいい?
➡️ その子のペースや特性を尊重し、安心できる環境をつくることが大切です。
小さな成功体験を褒めて自信を育てましょう😊
Q7: 家族以外のサポートはある?
➡️ 訪問看護、支援学校、地域の子育て支援団体、行政の福祉サービスなど様々なサポートがあります。
ひとりで抱え込まず、活用しましょう。
🎈 おわりに|診断名は“道しるべ”でしかない
「診断名=その子のすべて」ではありません。
でも私たちにとっては、子育ての方向性を示してくれる大切な道しるべになりました。
障害児育児は大変ですが、同時に小さな喜びは何倍にも感じられます。
そして今日も、私は息子から学んでいます——
「ゆっくりでも、ちゃんと育っている」
「笑顔は最強のコミュニケーション」
これが、今の私の宝物です💖
▼ 参考リンク(例)
- 厚生労働省「発達障害者支援法」について(自治体の相談窓口案内など)
- 地域の児童発達支援センター情報(自治体HP)
✨ この記事が、同じ悩みを抱えるママ・パパの安心や行動の一歩につながれば嬉しいです。
不安なときはひとりで抱え込まず、周囲の専門家や支援を積極的に活用してくださいね😊
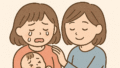
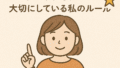
コメント