こんにちは😊障害児育児に奮闘中のさえゆきです。
今回は、私自身が経験した「障害児育児のしんどい時期」をどう乗り越えたのか、実体験をもとにシェアします。
同じように悩むママ・パパの力になれば嬉しいです!💖
- 1️⃣ 障害児育児の「しんどい時期」とは?😢
- 2️⃣ 私が感じた具体的な「しんどさ」📌
- 3️⃣ それでも乗り越えられた理由✨私の方法
- 4️⃣ 役立った支援制度まとめ📋
- 5️⃣ よくある質問(FAQ)❓
- 6️⃣ 最後に🌟
- Q1:障害児育児で一番初めにすべきことは何ですか?📝
- Q2:療育手帳や身体障害者手帳はどうやって申請すればいいですか?📋
- Q3:医療的ケア児向けの支援はどんなものがありますか?⚕️
- Q4:療育センターではどんな支援が受けられますか?🏥
- Q5:支援制度を使うことに罪悪感があります。どうしたらいいですか?💭
- Q6:同じような悩みを持つ親とのつながりはどう作ればいいですか?🤝
- Q7:育児のストレスや疲れをどうやって解消していますか?🌿
- Q8:支援施設に通う子どもの負担は心配です。どうすればいいですか?🏫
- Q9:将来のことが不安で眠れません。どう気持ちを整理したらいいですか?🌙
- Q10:どこに相談しても状況がよくわかってもらえません。どうしたら?🔍
1️⃣ 障害児育児の「しんどい時期」とは?😢
障害児育児は楽しいことも多い反面、特に初期は…
- 子どもの発達の遅れに戸惑う
- 病院や療育機関の手続きが多くて疲れる
- 周囲の理解が得られず孤独を感じる
- 子どもの体調不良に追われる
など、「しんどさ」がピークになる時期があります。
私も、息子の発達障害がわかってからの半年間は毎日が精神的にも肉体的にも限界でした。💔
2️⃣ 私が感じた具体的な「しんどさ」📌
- 言葉が遅くて、コミュニケーションが難しい
- 夜泣きや睡眠障害で寝不足が続く
- 家事・育児・療育の両立が難しい
- 周囲の偏見や無理解による孤立感
- 将来の不安でいっぱい
毎日、子どもの状態を見ながらの対応に、心も体もボロボロに…。
「もう無理かもしれない」と何度も思いました。😢
3️⃣ それでも乗り越えられた理由✨私の方法
① 専門家・支援機関に頼ることを決意🤝
- 市区町村の発達支援センターに相談
- 訪問看護・リハビリを積極的に活用
- 療育手帳や身体障害者手帳の申請
- 医療的ケア児支援センターの情報収集
最初は「自分で何とかしなきゃ」と思っていましたが、専門家に頼ることで、気持ちが楽になり、具体的な支援が得られました。
② 同じ境遇のママ友・支援グループに参加👩👩👧👦💬
- 不安や悩みを共有できる仲間ができた
- リアルな経験談や有益情報をもらえた
- SNSや地域の支援グループも活用
孤独感が和らぎ、前向きな気持ちを取り戻す大きな支えになりました。
③ 自分の心と体を大切にする🌸
- 完璧を目指さず、できることだけやる
- 疲れた日は家事を手抜きしてOK
- 時々は息抜きや趣味の時間を作る
- 専門家のカウンセリングを受けることも
「母親としてしっかりしなきゃ」というプレッシャーを減らし、自分を労わることで、持続可能な育児ができました。
④ 育児記録&成長の小さな変化に目を向ける📔✨
- 毎日の子どもの変化やできたことを記録
- 小さな成長や笑顔を大切にする
- ネガティブな気持ちを整理できる
振り返ることで、前向きな気持ちが生まれ、長期的なモチベーション維持につながりました。
4️⃣ 役立った支援制度まとめ📋
- 療育手帳・身体障害者手帳の申請で医療費助成や交通費割引
- 児童発達支援センターでの個別・集団療育
- 医療的ケア児支援(訪問看護、専門施設利用)
- 移動支援サービスで外出のサポート
- 家族支援サービスで一時預かりや相談支援
これらを活用することで、私の負担は大きく軽減されました。🌈
5️⃣ よくある質問(FAQ)❓
Q1:支援を受けるためには何から始めればいい?
➡️ お住まいの市区町村の保健センターや子ども家庭支援センターに相談しましょう。無料相談窓口もあります。
Q2:療育手帳はどうやって申請するの?
➡️ 医師の診断書をもとに自治体の福祉課へ申請します。申請方法は自治体によって異なります。
Q3:医療的ケア児向けのサービスはある?
➡️ あります。看護師常駐の施設や訪問看護が利用可能です。支援センターに問い合わせましょう。
Q4:支援グループにはどうやって参加する?
➡️ SNSや市の福祉課、療育センターに情報があります。口コミでつながる場合も。
Q5:精神的に辛いときはどうしたら?
➡️ カウンセリングや障害児ママ向けのサポート窓口を利用してください。ひとりで抱え込まないことが大切です。
6️⃣ 最後に🌟
障害児育児は確かに「しんどい時期」があります。
でも、それを乗り越えられたからこそ、今の笑顔や小さな成長が輝いて見えます。✨
ひとりで抱え込まず、専門家や支援制度、仲間の力を借りて、少しずつ歩んでいきましょう。
あなたの頑張りは必ず子どもに届いています。💖
✨もしこの記事が少しでもあなたの励みになったら嬉しいです。
コメントやシェアも大歓迎!😊
よくある質問(FAQ)❓
Q1:障害児育児で一番初めにすべきことは何ですか?📝
A: まずはお住まいの市区町村の保健センターや子ども家庭支援センターに相談することが大切です。発達の遅れや障害の可能性がある場合は早めの専門機関受診も検討しましょう。
Q2:療育手帳や身体障害者手帳はどうやって申請すればいいですか?📋
A: 医師の診断書を基に自治体の福祉課や障害者支援窓口で申請します。自治体によって申請方法や必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
Q3:医療的ケア児向けの支援はどんなものがありますか?⚕️
A: 看護師常駐の保育施設や訪問看護ステーションの利用、専門相談窓口の設置などがあります。市区町村の窓口で「対応が難しい」と言われた場合は、県や広域支援センターにも問い合わせてみてください。
Q4:療育センターではどんな支援が受けられますか?🏥
A: 発達検査、作業療法や言語療法などの専門的な支援、保護者同士の交流や相談も可能です。子どもの特性に合った療育計画を立ててくれます。
Q5:支援制度を使うことに罪悪感があります。どうしたらいいですか?💭
A: 支援制度は困っている家庭のためにあります。頼ることは甘えではなく、子どもにとっても親にとっても大切なこと。心の余裕が子どもの成長にプラスになると考えましょう。
Q6:同じような悩みを持つ親とのつながりはどう作ればいいですか?🤝
A: 地域の親子教室や支援グループ、SNSの障害児育児コミュニティなどがあります。自治体の福祉課や療育センターで情報を聞くのもおすすめです。
Q7:育児のストレスや疲れをどうやって解消していますか?🌿
A: 体を休める時間を作る、趣味に没頭する、専門のカウンセリングを受けるなど、自分を労わる時間を意識的に確保しています。ひとりで抱え込まないことが大切です。
Q8:支援施設に通う子どもの負担は心配です。どうすればいいですか?🏫
A: 初めは緊張や不安もありますが、徐々に環境に慣れ、楽しみを見つける子どもも多いです。施設スタッフと連携し、子どものペースを尊重しましょう。
Q9:将来のことが不安で眠れません。どう気持ちを整理したらいいですか?🌙
A: 不安は誰でも感じます。専門家や同じ境遇の親と話すことで気持ちが軽くなります。また、今できることに集中し、小さな成長を喜ぶことで前向きになれます。
Q10:どこに相談しても状況がよくわかってもらえません。どうしたら?🔍
A: 地域によって支援の充実度に差があります。市町村で難しい場合は県や広域支援センター、NPO団体など他の相談窓口を探してみるとよいです。


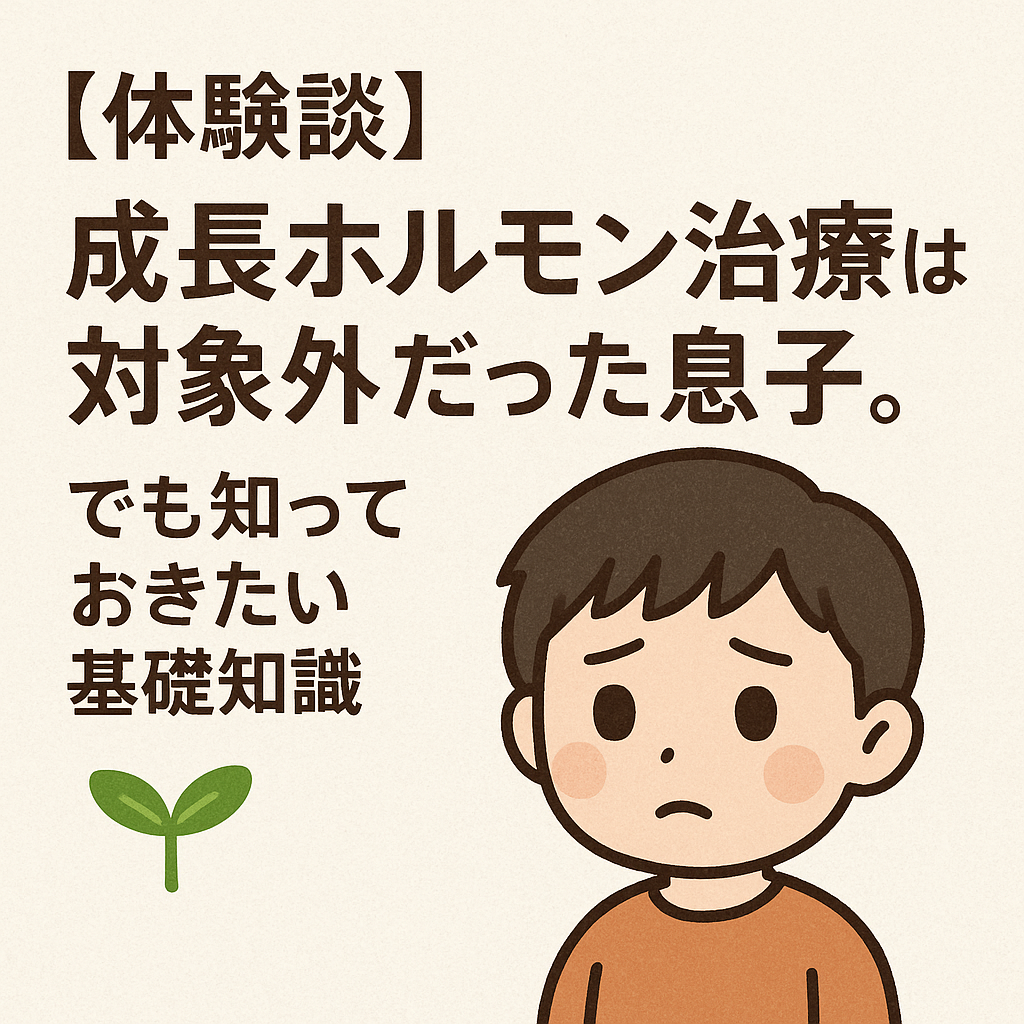
コメント