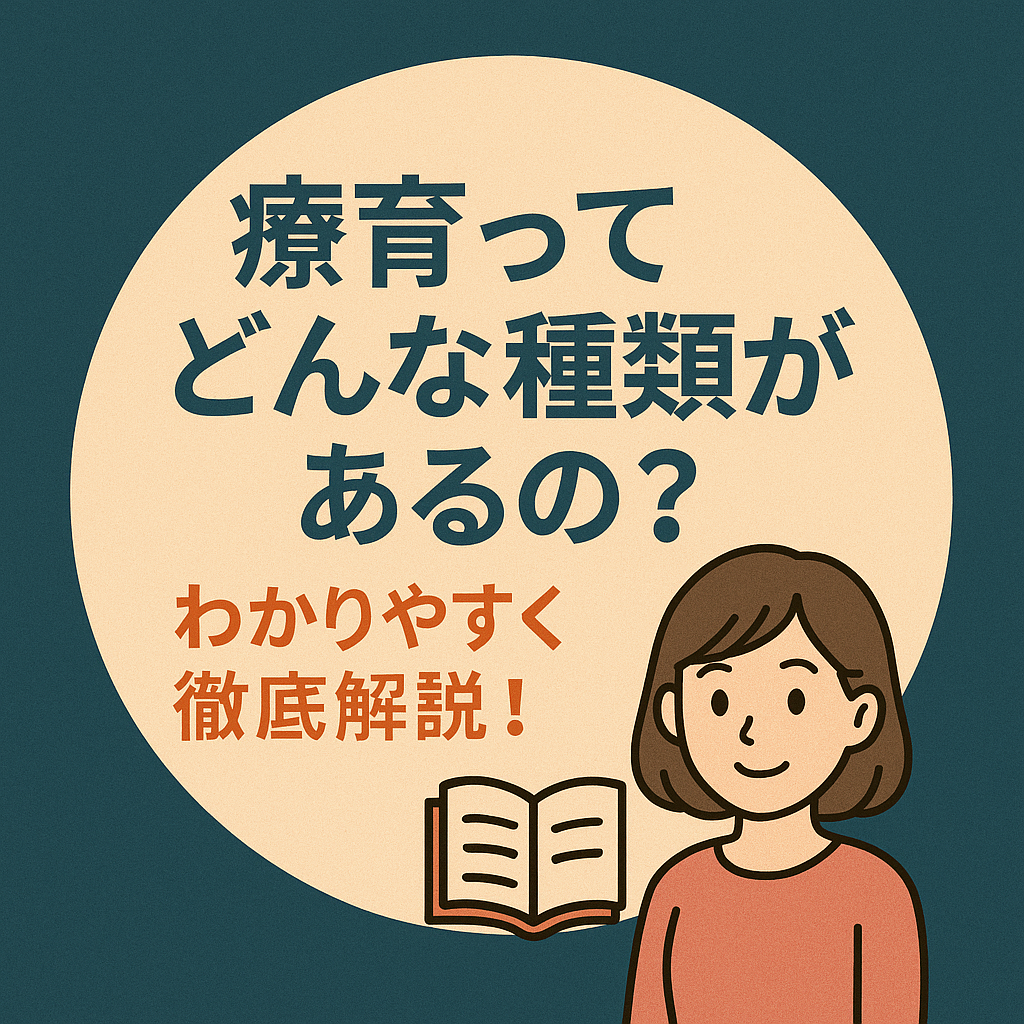
🧒「療育ってよく聞くけど、実際どう選べばいいの?」と悩むあなたへ
お子さんの発達に気になる点が出てくると、耳にするのが「療育」という言葉。
でも、いざ調べてみると…
- 「種類が多くて違いがよくわからない」
- 「うちの子に合うタイプってどれ?」
- 「支援内容って本当に効果あるの?」
と、戸惑う保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、【療育の主な4つの種類と特徴】を、わが家の体験談+専門解説付きでわかりやすく解説します。
🔍 療育とは?意味と目的をやさしく解説
療育(りょういく)とは、発達の遅れや特性をもつ子どもが、自分らしく生きる力を身につけていくための支援です。
- 専門の支援員(保育士・療法士・心理士など)が、
- 遊びや日常生活を通じて、
- コミュニケーション・運動・感情の発達をサポート
本人の「できること」を増やして、自信や社会性を育むのが大きな目的です。
🧩主な療育の4タイプ|特徴・向いている子ども像
① 療育園(医療型・福祉型)
特徴
- 医療的ケアやリハビリを受けながら通う日中施設
- 作業療法士(OT)・理学療法士(PT)・言語聴覚士(ST)などの専門職が常駐
- 看護師によるサポートや健康管理あり
向いている子ども
- 医療的ケアが必要
- 重度の発達障害がある
- 通所でのリハビリを希望している
② 児童発達支援【個別型】
特徴
- 支援員とマンツーマンの個別療育
- 言葉や行動、感覚過敏など、1人ひとりに応じた課題設定が可能
- 発達検査の結果や家庭の希望に合わせて対応
向いている子ども
- 刺激に敏感・こだわりが強い
- 集団にストレスを感じる
- 指示理解に時間がかかる
③ 児童発達支援【個別+集団型】
特徴
- 個別支援+小集団での活動の両方を体験できる
- ステップアップを意識した支援設計がされている
- 療育の入口としても人気
向いている子ども
- 少しずつ集団に慣れていきたい
- 同年齢の子と関わる経験をさせたい
- 「できた!」の経験を重ねたい
④ 児童発達支援【集団型+外出支援あり】
特徴
- 公園や公共施設での実地支援も含む「社会経験重視」型
- 交通ルールや集団行動、外食練習なども取り入れる
- 就園・就学前の「準備の場」として選ばれることが多い
向いている子ども
- 集団生活の練習がしたい
- 公共の場でのふるまいを学びたい
- 幼稚園・小学校のステップを意識したい
📖【体験談】うちの子に合う療育の見つけ方|シングルマザーの選択
我が家の息子は、極低出生体重児で生まれ、現在は脳性まひの診断を受けています。3歳で障害者手帳を取得し、発語はなく、運動機能に重い障害があります。
はじめは「個別型」を選択しましたが、息子にとっては集団活動の刺激や“他の子どもの存在”が安心材料になることが分かり、後に「個別+集団型」に切り替えました。
今では、週5回の児童発達支援+訪問PT・OTでバランスをとっています。
🧭 療育を選ぶときのチェックポイント5つ
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 子どもの特性に合っているか? | 感覚過敏・注意力・運動機能などを考慮 |
| 通いやすさは? | 自宅からの距離・送迎の有無・時間帯など |
| スタッフとの相性 | 話しやすい・信頼できる雰囲気があるか |
| 見学・体験ができるか? | 子どもの反応を見る機会があるか |
| 利用者の口コミや評判 | SNSや他の親の意見も参考に |
❓よくある質問(FAQ)
Q. 療育って何歳から受けられるの?
A. 基本的には0歳から利用可能です。多くの施設は1歳半〜3歳頃からの受け入れが多く、早期支援が推奨されています。
Q. 療育は受けないといけないの?
A. 義務ではありませんが、発達の特性がある場合は「環境を整える」ことが非常に重要です。受けることで家庭の育児ストレスが減ることもあります。
Q. 費用はかかりますか?
A. 多くの場合、福祉サービス利用で1割負担+月上限あり(世帯所得に応じて変動)です。実質無料に近い家庭もあります。
🌈まとめ|療育は“相性”と“出会い”がすべて
療育にはたくさんのスタイルがありますが、「これが正解」というものはありません。
大切なのは、お子さんとご家族が「ここなら安心」と思える場所を選ぶこと。
まずは、迷っている段階でも見学・相談してみることが第一歩です。
支援者は、あなたとお子さんを応援する“味方”です。
焦らず、一歩ずつ選んでいきましょう。


コメント