~早産児・低緊張・リハビリ・補償制度…3歳5ヶ月での診断まで~
こんにちは。「療育ママのひとりじゃない」へようこそ。
私は40代で出産し、現在は一人で、脳性麻痺と診断された息子を育てています。
脳梗塞の後遺症を抱えながらも、息子と共に毎日を生きる中で経験したリハビリや医療との関わり、診断名に揺れる心情…。
この記事では、同じような状況で悩む方に向けて、わが家の3年間のリアルな記録を綴ります。
🐣生後8ヶ月からの外来リハビリ開始
早産で生まれた息子。退院後の成長に不安を感じていた私に、医師が勧めてくれたのが外来リハビリ(PT)でした。
📅 開始時期:生後8ヶ月
👩⚕️ 主治医の指示:「発達の程度に関わらず、階段昇降ができる(2歳前後)まで継続を」
「障害」とは診断されていない段階でしたが、「早めに始めることに意味がある」と背中を押されました。
🧠2歳7ヶ月でリハビリ週1へ|PT変更も経験
息子が2歳7ヶ月を迎えた頃、外来リハビリが週1回に増加。
そして、このタイミングでPT(理学療法士)の担当変更がありました。
子どもが環境や人に敏感な年齢だからこそ、この変更は親子ともに大きな出来事でした。
🏥3歳5ヶ月|訪問看護への切り替えと再受診
現在、息子は3歳5ヶ月。
病院での外来リハビリを卒業し、訪問看護でのPT・OTをスタートするにあたり、出生病院へ受診。
目的は「訪問看護に必要な主治医指示書の取得」。
その場で主治医から正式に伝えられたのが——
📖「脳性麻痺」という診断名
私:「整形外科で“脳性麻痺”と診断されました」
主治医:「脳性麻痺は“病気の名前”ではなく、“永続的な運動機能障害”を示す“症候名”です。MRIで損傷が見つからなくても、3歳を過ぎて歩行が困難な場合、脳性麻痺と診断されます」
🧸「重度の低緊張」でも歩ける希望は?
整形外科では「芯がない」「ふにゃふにゃ」という言葉が使われました。
小学校入学時には車いす利用の可能性があるとも言われ…。
医師の言葉:
「現在の発達状況は横ばいか、それに近い。障害者手帳では2級相当。現時点で歩行の獲得は厳しいと考えられます」
💸産科医療補償制度の申請とタイミング
私は迷っていました。
- 息子は3歳で「つかまり立ち」はできるが、「歩行」は難しい
- でも、4歳の診断基準では「独歩ができない」が対象になる…
医師の見解:
「申請は可能。ただし、3歳では対象外となる可能性が高い。
4歳時点での再申請を検討してもよい。
ただし、補償金を“成長ホルモン治療”に使うことには否定的です」
🧪成長ホルモン検査のタイミングと考え方
医師からは、成長ホルモン検査について以下のような助言がありました:
- 現在の数値(8〜14)は保険対象外(6以下が基準)
- ただし1年後に対象となる可能性あり
- 半年ごとの検査にはあまり意味がないため、1年おきの再検査が望ましい
🚼 掴まり立ち=歩けるではない?
私は「掴まり立ちができれば歩けるようになる」という話を聞いて、期待していました。
でも医師はこう説明しました:
「息子さんのように、低緊張や体幹の未発達が著しい場合、掴まり立ちができても歩行に至らないケースはあります。
MRIに損傷がないのも非常に稀。
遺伝子検査・染色体検査も正常ということで、奇跡的な成長の爆発が起こる可能性も否定できません」
🏫将来の学校選択は?支援学校について
「小学校は支援学校になるのでしょうか?」という私の質問に、主治医はこう答えました:
「最終的には就学前診断の結果で判断されます。まだ時間があります。焦らず、今できることを大切にしましょう」
🍀NICUからの主治医と、これからも
この医師は、NICU入院中から息子を診てくれている先生。
「小さい以外に異常はない」と言い続けてくださっていた、信頼できる存在です。
だからこそ、この「脳性麻痺」という言葉を受け止められたのかもしれません。
❓よくある質問(FAQ)
Q. 脳性麻痺はMRIで診断されますか?
A. 必ずしもそうではありません。MRIに異常がなくても、「3歳を過ぎても独歩できない」などの症状があれば診断されることがあります。
Q. 補償制度は3歳を過ぎると使えませんか?
A. 3歳で対象外でも、4歳で再申請が可能な場合があります。医師に相談しながら判断しましょう。
Q. 成長ホルモン治療で歩けるようになりますか?
A. 身長の伸びには効果がありますが、歩行への直接的な効果は証明されていません。
✨あとがき|それでも、前を向いて
私たちは今、「奇跡があるかもしれない」という一筋の希望を胸に、今日も療育と向き合っています。
障害の程度や診断名よりも、「目の前のこの子と、どう生きていくか」が私たちにとって一番大切なこと。
この記録が、誰かの心を少しでも軽くできますように。


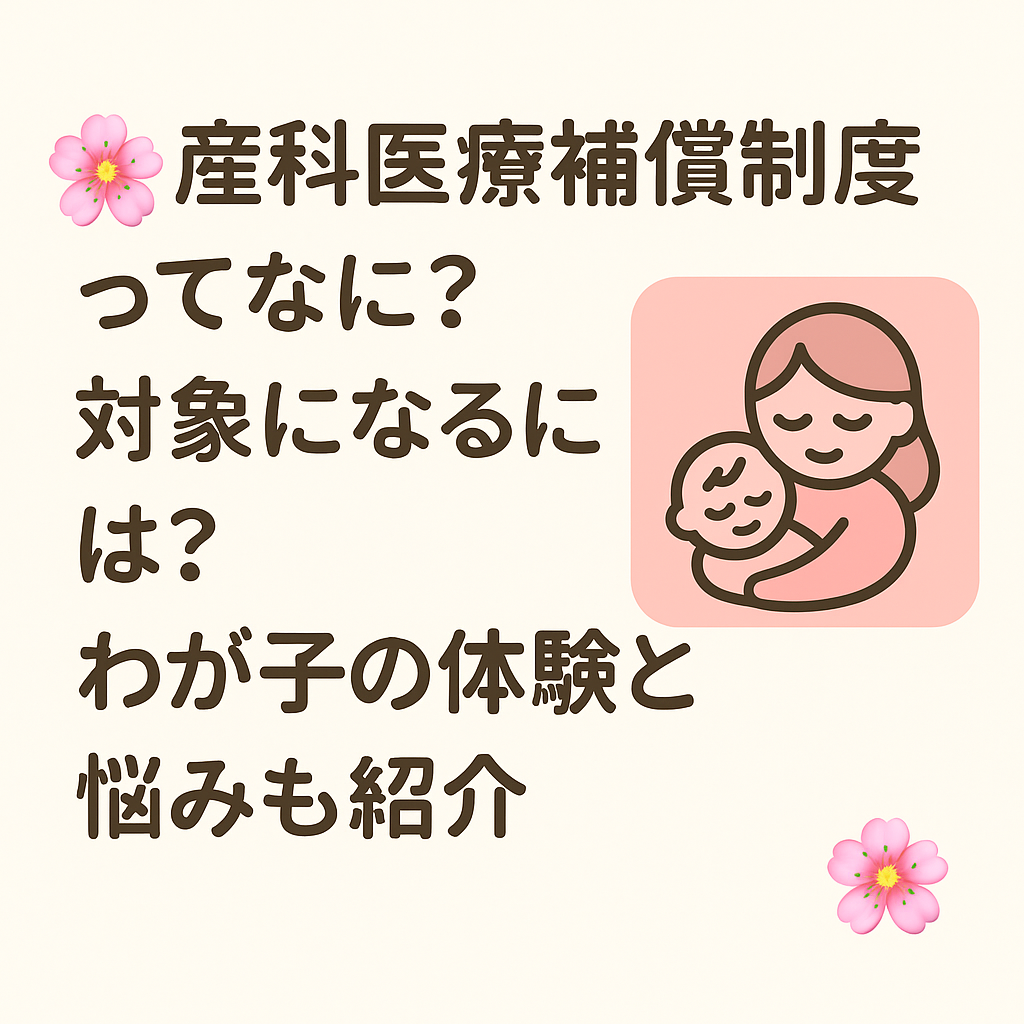
コメント