【体験談】発語が遅い?焦らないで!脳性まひの息子と試した言葉を育む10の工夫と専門家の知見
「うちの子、まだ話さない…」「周りの子と比べて言葉が遅いかも…」
発語がゆっくりな子どもを育てる中で、そんな不安や焦りを感じることはありませんか?私自身も、脳性まひを持つ発語がゆっくりな息子と向き合い、試行錯誤の日々を送ってきました。
この記事では、発語が遅い原因や発達の目安といった基礎知識から、我が家で実践して効果があった具体的な方法、さらには専門家(言語聴覚士)から教わった関わり方のコツまで、網羅的に解説します。読者の方が今日から実践できるヒントがきっと見つかります。
【結論】発語の遅れは個人差が大きい。でも不安なら専門家へ
子どもの成長は一人ひとり違います。言葉の発達も同様で、目安通りに進まなくても、その子のペースで成長しているケースがほとんどです。しかし、保護者として「何かできることはないか」「専門家の意見も聞きたい」と感じるのは自然なことです。
この記事で紹介する方法を試しながら、もし不安が続くようであれば、お住まいの自治体の発達支援センターや保健センター、かかりつけの小児科などへ気軽に相談してみてください。
公的情報でさらに安心
言葉の発達に関する一般的な情報は、公的な機関からも発信されています。より詳しい情報を知りたい方は、以下のサイトも参考にしてみてください。
- 厚生労働省 e-ヘルスネット:「子どもの心の成長と発達」
- 国立成育医療研究センター:「ことばの発達の遅れ」
※上記は一例です。詳しくは各公式サイトをご確認ください。
発語が遅いかも?申請の前に知っておきたい基礎知識
一般的な発語の発達目安
まず、一般的な言葉の発達の目安を知っておきましょう。ただし、これはあくまで目安であり、個人差が非常に大きいことを念頭に置いてください。
- 1歳前後:意味のある単語が1〜2語出始める(例:「ママ」「ブーブー」)
- 2歳頃:「ママ、きて」のような二語文が出始める
- 3歳頃:簡単な会話ができるようになる
言葉が遅れる原因はさまざま
発語がゆっくりになる背景には、さまざまな要因が考えられます。
- 発達のペース:単純に、その子の成長のペースがゆっくりな場合。
- 身体的な要因:聴覚や、口・舌の動きといった口腔機能に課題がある場合。
- 環境的な要因:家庭内での言葉の刺激が少ない、または、きょうだいが代弁してしまうなど。
- 発達特性:自閉スペクトラム症や言語発達遅滞などの特性が背景にある場合。
【専門家直伝】今日からできる!発語を促す10の工夫
ここからは、言語聴覚士さんから教わったアドバイスと、我が家で実践した方法を合わせて10個ご紹介します。
①【基本のキ】ゆっくり・はっきり・短く話す
大人が早口で話すと、子どもは言葉を聞き取って意味を理解するのが難しくなります。「これは、りんご。あかいね。」のように、一文を短く区切り、ゆっくりはっきり話すことで、子どもは言葉をインプットしやすくなります。
💬 私の体験談
意識してゆっくり話すように変えただけで、息子が私の口元を見て、一生懸命聞き取ろうとする姿勢を見せてくれるようになりました。視線が合う回数が増え、コミュニケーションの土台ができたと感じます。
② ジェスチャーや表情を豊かに
言葉は音だけではありません。「バイバイ」と手を振る、「おいしい」と笑顔になるなど、ジェスチャーや表情は言葉の意味を補強する強力なツールです。非言語的なコミュニケーションが、言語理解の助けになります。
③ 親子で楽しむ絵本の読み聞かせ
絵本は新しい言葉の宝庫です。特に、擬音語(ワンワン、ブーブー)や繰り返しのあるストーリーは、子どもの興味を引きやすく、発語のきっかけになりやすいと言われています。
💬 私の体験談
息子は動物の鳴き声が出てくる絵本が大好きでした。最初は指さしだけでしたが、何度も読むうちに「ぞう!」と初めて意味のある言葉を発してくれた日の感動は今でも忘れられません。
④ 歌や手遊びでリズムに乗る
歌のメロディーやリズムは、言葉を記憶しやすくする効果があります。「きらきら星」や「むすんでひらいて」など、動きを伴う手遊び歌は、楽しみながら言葉と体の動きを結びつける練習になります。
⑤ 「共感の指さし」を大切に
子どもが指をさしたものを、親も一緒に指をさして「あ、わんわんだね」と名前を教えてあげましょう。同じものを見て気持ちを共有するこの経験は、「伝えたい」という意欲を育てます。
⑥ 遊びに言葉を実況中継
子どもが集中している遊びに、言葉を添えてあげましょう。ブロックを積んでいたら「たかいね」、ミニカーを走らせていたら「ブーブー、はやいね」など、子どもの行動を実況中継することで、言葉と行動が結びつきます。
⑦ 「どっち?」で選ばせる
「おやつ、何がいい?」と聞くのではなく、「おせんべいとバナナ、どっちがいい?」と二択で質問してみましょう。子どもは答えやすくなり、自分の意思を言葉(または指さし)で伝える練習になります。
⑧ 言い間違いは優しく訂正
子どもが「ちゃかな(さかな)」などと言い間違えても、「違うでしょ」と否定するのはNGです。「そうだね、お魚さんだね」と、正しい言葉をさりげなく聞かせてあげるだけで十分です。話そうとした意欲を褒めることが大切です。
⑨ 生活の中で言葉を繰り返す
「くっく(靴)、はこうね」「くっく、ぬいだね」のように、日常生活の中で同じ言葉を何度も使うことで、言葉は定着しやすくなります。
⑩ 「沈黙の時間」を恐れない
親が質問した後、子どもが答えるのを待てずに、つい先回りして話してしまいがちです。質問したら5秒ほど待ってみましょう。子どもが自分で考えて言葉を絞り出すための、大切な「間」になります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 何歳になっても言葉が出なかったら相談すべき?
A1. 2歳半~3歳ごろになっても意味のある単語がほとんど出ない、簡単な指示が通りにくい、音への反応が乏しいなどの様子が見られる場合は、一度専門機関に相談することをおすすめします。かかりつけの小児科医や、お住まいの地域の保健センター、子ども発達支援センターなどが相談窓口となります。
Q2. 家庭での関わりと「療育」、どちらが大事?
A2. どちらも非常に大切で、両輪と考えるのが良いでしょう。家庭での関わりは、子どもが安心して言葉を育むための土台となります。一方で、療育では言語聴覚士などの専門家から、その子に合った個別のサポートを受けることができます。家庭での工夫に行き詰まったら、療育という選択肢を検討してみてください。
Q3. 親の焦りは子どもに伝わりますか?
A3. はい、伝わります。「早く話してほしい」というプレッシャーは、子どもにとって言葉を発することへの不安につながることがあります。親がリラックスして、笑顔で関わることが、子どもにとって何よりの安心材料になります。
まとめ:焦らず、子どものペースで。笑顔のコミュニケーションを大切に
発語を促すための工夫を10個ご紹介しましたが、最も大切なのは「親子でコミュニケーションを楽しむこと」です。
周りと比べる必要はありません。昨日より今日、ほんの少しでも指さしが増えた、目が合った、喃語が出た。そんな小さな成長を見つけて、たくさん褒めてあげてください。
この記事が、発語に悩む親御さんの心を少しでも軽くし、お子さんとの関わりをより豊かなものにする一助となれば幸いです🌱💕
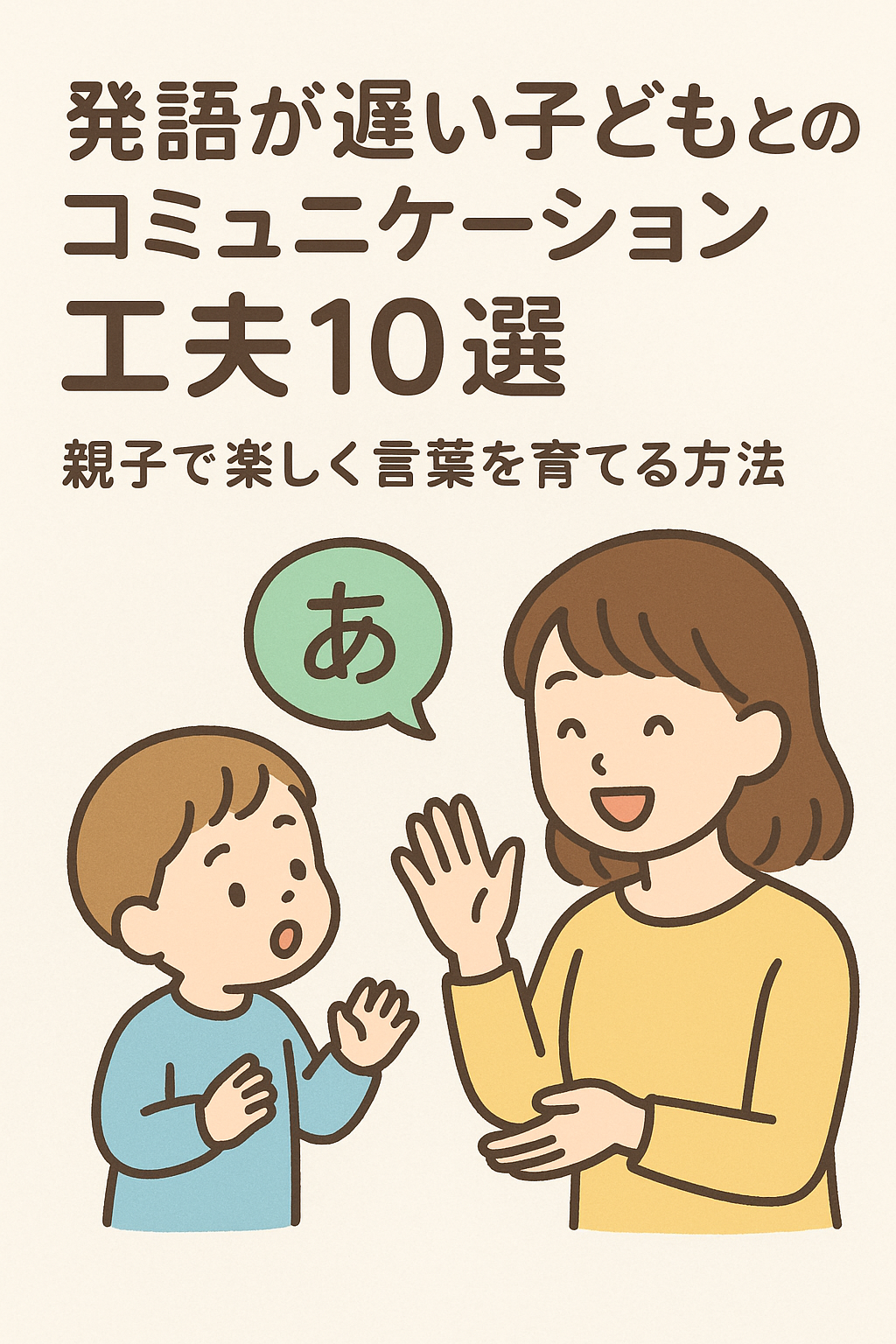

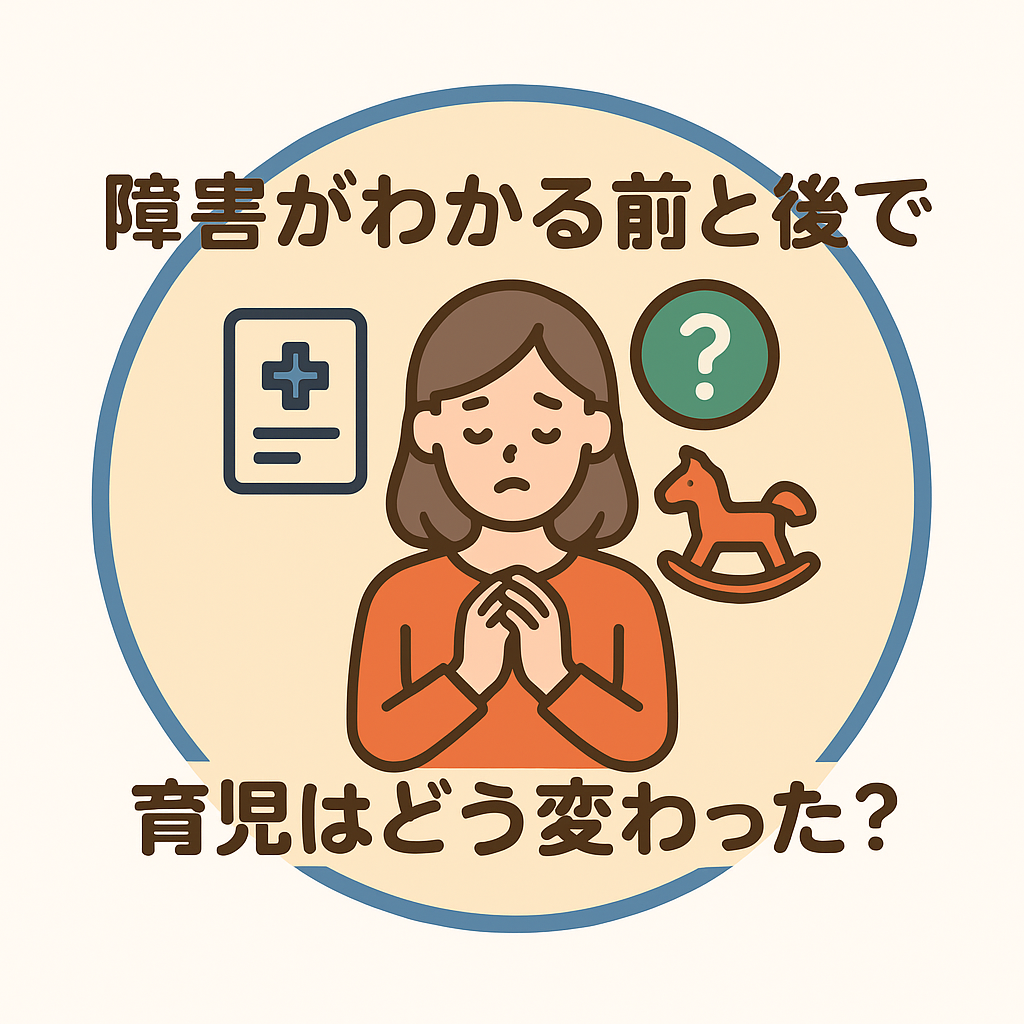
コメント