はじめに
障害児育児は、想像以上に心身ともに負担が大きく、時に母親としての葛藤や孤独感に襲われることも多いものです。
私の息子は脳性麻痺と診断され、生まれてから今日まで、たくさんの悩みや苦しみを経験しました。
この記事では、私自身の体験をもとに、母親としての葛藤の正体や向き合い方、心のケア方法をリアルにお伝えします。
さらに、療育や支援制度の基礎知識や具体的な相談先情報もまとめました。
同じような状況で苦しむお母さんたちの心の支えとなることを願っています。
1章|障害児育児で私が感じた「母親としての葛藤」
1-1. 「完璧を求めすぎて疲弊する自分」
障害児育児はやることが多く、「できることは全部やらなきゃ」と使命感が強くなります。
私も最初は完璧を目指し、療育・医療・福祉サービスをフル活用しました。
でもその頑張りが裏目に出て、自分の体と心を追い詰めてしまいました。
完璧を求めすぎてしまうと、自分を責めたり焦ったりで、母親としてもつらくなります。
1-2. 他の子どもや家庭と比較してしまう罪悪感
SNSや療育先でほかの子を見ては比べてしまい、落ち込む日々もありました。
「どうしてうちの子はまだ歩けないの?」
「他のママはうまくやっているのに、自分はダメなのかも…」
そんな自己否定の感情にさいなまれ、心が擦り減っていきました。
1-3. 未来への不安と焦りの連続
障害児の将来は未知数で、経済的・生活面の不安は常につきまといます。
- 学校や就労のこと
- 独立生活の支援
- 継続的な医療費の負担
先の見えない道に不安が募り、焦りを感じることもありました。
2章|葛藤を乗り越えるために私が実践した心の向き合い方
2-1. 完璧主義を手放す勇気を持つ
「100点でなくていい。70点でも十分」
この考え方が心の余裕を生みました。
子どもと自分のペースを尊重し、できることに集中することが大切です。
2-2. 同じ境遇のママと繋がり孤独を和らげる
孤独感は大きなストレスの原因。
地域の親の会、SNSの支援グループなどで共感を得られると救われます。
2-3. 自分の心と体を大切にする時間を作る
短時間でもいいので自分だけの時間を持つことが重要です。
- 散歩🚶♀️
- 好きな音楽を聴く🎵
- 趣味に没頭する
これだけでも心身のリセットになります。
3章|療育と支援制度の基礎知識
3-1. 療育とは何か?
療育は障害児の発達支援のこと。
理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語療法(ST)など多岐にわたります。
3-2. 児童発達支援事業(児発)
0〜6歳を対象に、専門スタッフが子どもの発達に合わせて支援します。
3-3. 産科医療補償制度
低酸素脳症など特定の産科トラブルによる障害に対し、補償金が支払われる制度。
申請条件や申請方法、個別審査のポイントなど複雑なので、詳しくは産科医療補償制度の窓口に相談しましょう。
4章|具体的な相談先・支援機関リスト
4-1. 地域の障害児支援センター
療育相談、福祉制度案内、専門機関紹介を行っています。
4-2. 心療内科・カウンセリング機関
母親の心のケアに重要です。近くの医療機関を調べて早めに相談しましょう。
4-3. 障害児支援のNPO・オンラインコミュニティ
SNSやネット上の支援グループも気軽に参加できておすすめです。
5章|よくある質問(FAQ)
Q1. 心がつらい時、どうすれば?
A1. 専門機関の利用や信頼できる人に話すことが大切です。ひとりで抱え込まないで。
Q2. 子どもと他の子の違いがつらいです。
A2. 比較はやめ、日々の成長に目を向けましょう。小さなできたことに喜びを見つけて。
Q3. 支援制度はどう調べればいい?
A3. 市区町村の障害児支援窓口や障害児支援センターに相談しましょう。
まとめ
障害児育児は過酷ですが、決して一人で抱え込まないでください。
葛藤を認め、心を大切にしながら、支援制度や仲間の力を借りて歩み続けましょう。
あなたの頑張りは必ず子どもの未来に繋がっています。
🌟もしこの記事があなたの心に届いたなら、ぜひ周りのママにもシェアしてください。

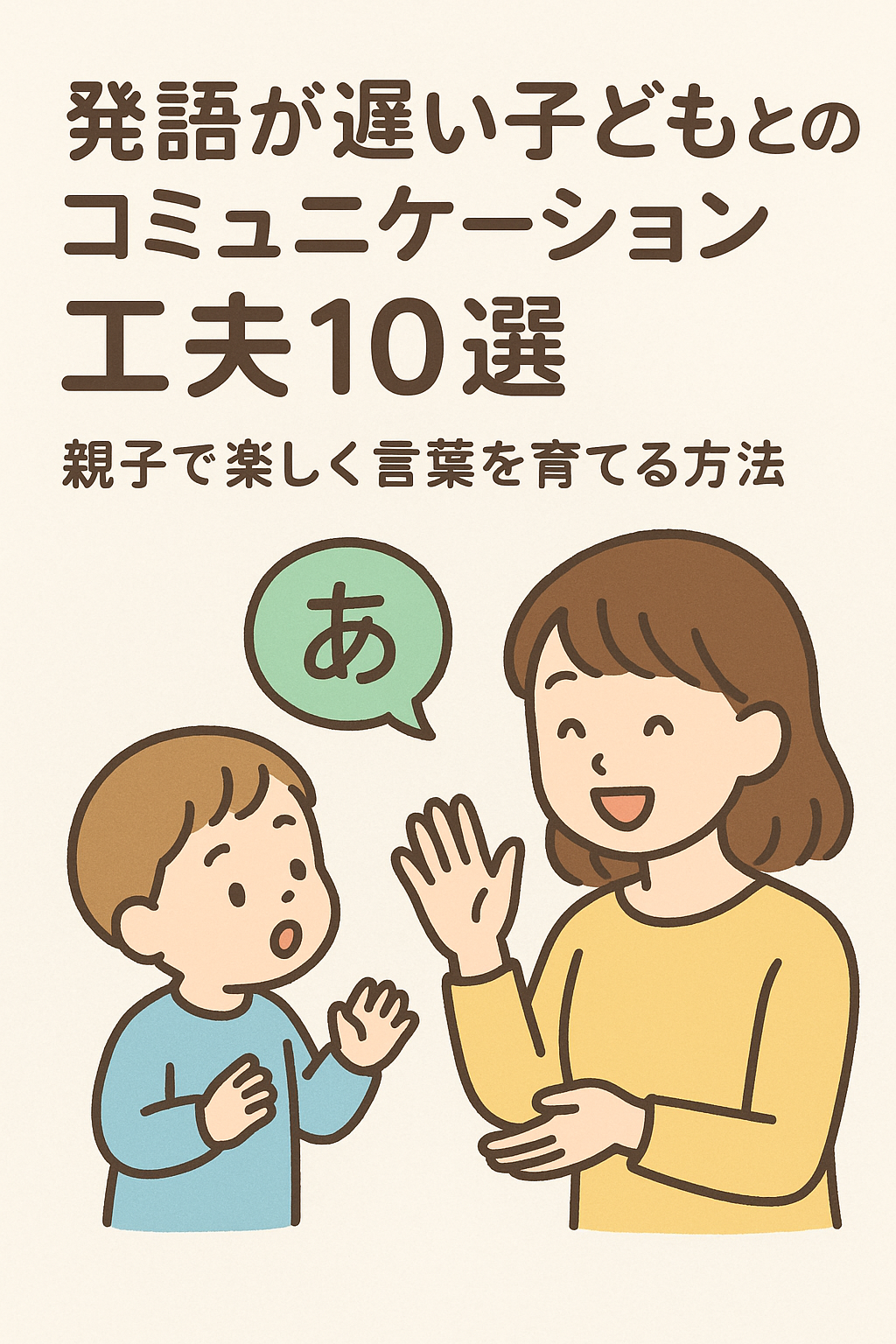
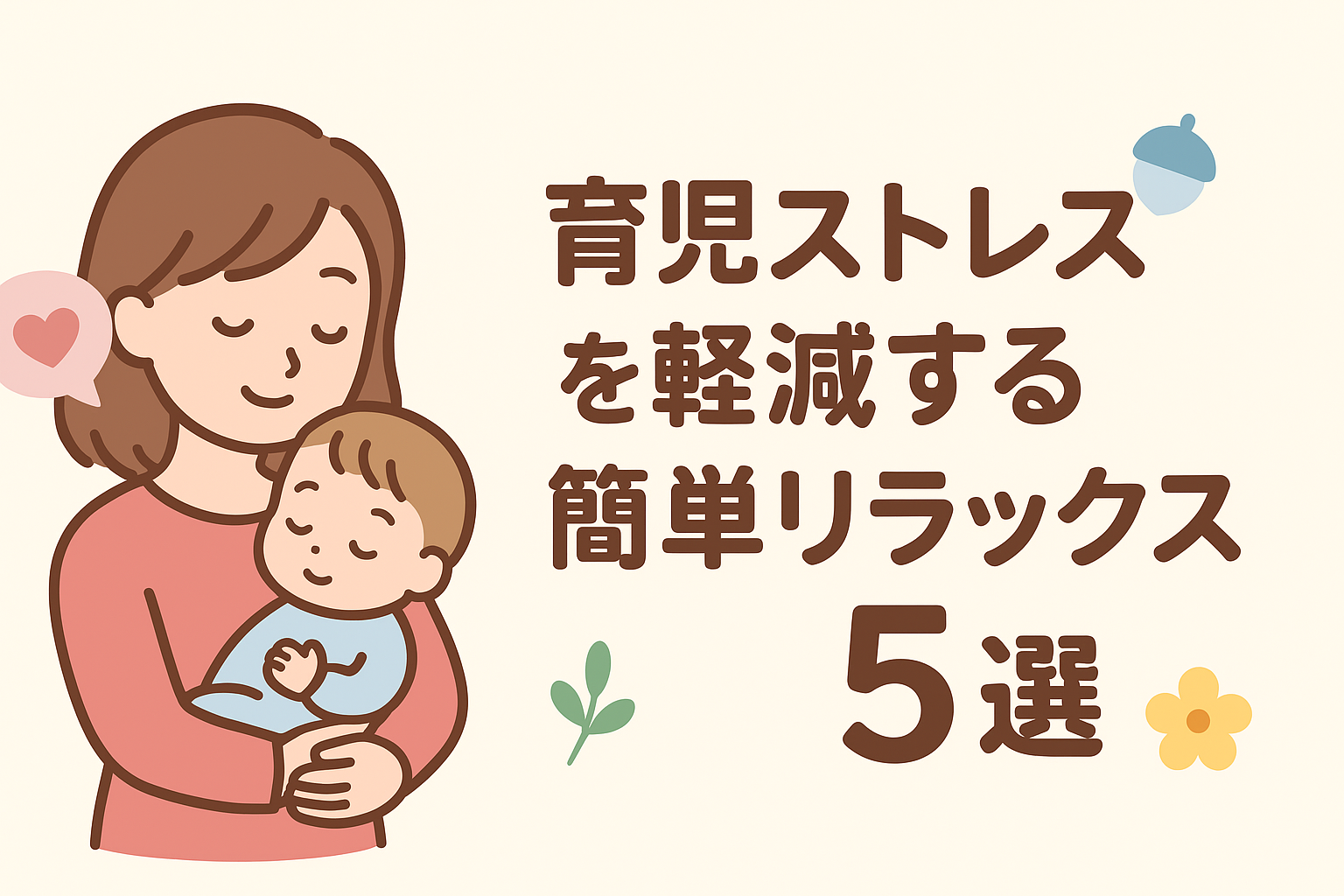
コメント