私の心と暮らしのリアルな変化
🌱 気づいた「小さな違和感」から始まった日々
「ちょっと遅れてるのかな?」
そう思い始めたのは、1歳半を過ぎた頃でした。
周りの子が指差しや言葉を少しずつ話し始めているのに、うちの子は音の出るおもちゃをじっと見つめてばかり。最初は「個性だよね」「成長には個人差があるし」と自分に言い聞かせていました。でも、どこかで“何か違うかもしれない”という不安が膨らんでいったのを覚えています。
誰かに相談するのが怖かった。
だって「気にしすぎ」と笑われるか、「やっぱりね」と言われるか、どちらにしても受け止められる自信がなかったからです。
🧠 診断を受けた日のことを、今でも覚えている。
3歳1ヵ月で、小児整形外科の先生から「脳性麻痺」(体幹機能不全・知的障害)と診断が下されました。
帰り道、診断書をバッグにしまいながら、涙が止まりませんでした。
「この子にとって、この先の人生はどうなっていくの?」
「私はちゃんと支えられるの?」
そんな不安が頭をぐるぐるめぐっていました。
シングルマザーである私は、ひとりでこの気持ちをかかえるしかありませんでした。
💬 期待と不安で揺れた、療育との向き合い
療育センターに通い始め初日はとにかく緊張して、他の親御さんたちとどんな距離感で接すればいいのかもわかりませんでした。
でも、保育士の方が子どもに寄り添って接してくれる姿に、ほっとしたのを覚えています。
「ああ、この子はひとりじゃない。私も、支えてくれる人がいるんだ」と。
一方で、通う中で感じる焦りや落ち込みもありました。
同じ年の子が会話をしていたり、工作をしていたりするのを見ると、どうしても比べてしまう自分がいたからです。
ただ、子どもが少しずつできることを増やしていく姿を目の当たりにするうちに、
「この子のペースを大事にしよう」と思えるようになりました。
🕒 生活リズムと優先順位がガラリと変わった
障害がわかる前と後では、暮らしそのものが変わりました。
例えば、毎週の療育通いや定期的な通院がスケジュールの中心になり、働きにでることはできなくなりました。
家事の効率を上げるために家電を見直したり、支援制度を活用したりと、
「自分だけで抱えない工夫」を意識し始めました。
また、家族との時間の過ごし方も大きく変わりました。
週末は公園や図書館ではなく、療育施設のイベントに参加したり、感覚過敏に配慮した静かな場所を選んだり。
以前のような“普通のレジャー”ではなく、
“この子が心地よく過ごせる時間”が一番になりました。
💖 それでも育児は“愛情を育てる時間”だった
障害があるからといって、育児の本質が変わったわけではありません。
むしろ、「この子を全力で支えたい」という気持ちは、より強くなった気がします。
発語はないけれど、目を見て笑ってくれるようになったときの喜び。
着替えを嫌がっていた子が、自分で靴下を脱げた瞬間。
そういう「他の人にとっては当たり前かもしれないこと」が、わが家では“祝福の時間”でした。
私は今でも、子どものノートに「できたこと日記」を書いています。
どんなに小さな成長でも、「今日はこれができたね」と一緒に喜ぶ時間が、私にとってかけがえのないご褒美なんです。
📝 おわりに|「違う育児」ではなく「この子に合った育児」
障害がわかってからの育児は、たしかに大変なことも多いです。
でもそれは「特別な育児」ではなく、「この子に合った育て方」をしているだけ。
私自身、完璧な母親ではありません。
たまにはイライラもするし、泣きたくなる夜もあります。
でも、そんな私でも、子どもは無条件に笑ってくれる。抱きついてきてくれる。
だから、これからもこの子と一緒に、
小さな幸せを一歩ずつ積み重ねていこうと思っています。
“育てる”というより、
“一緒に育っていく”という感覚で。
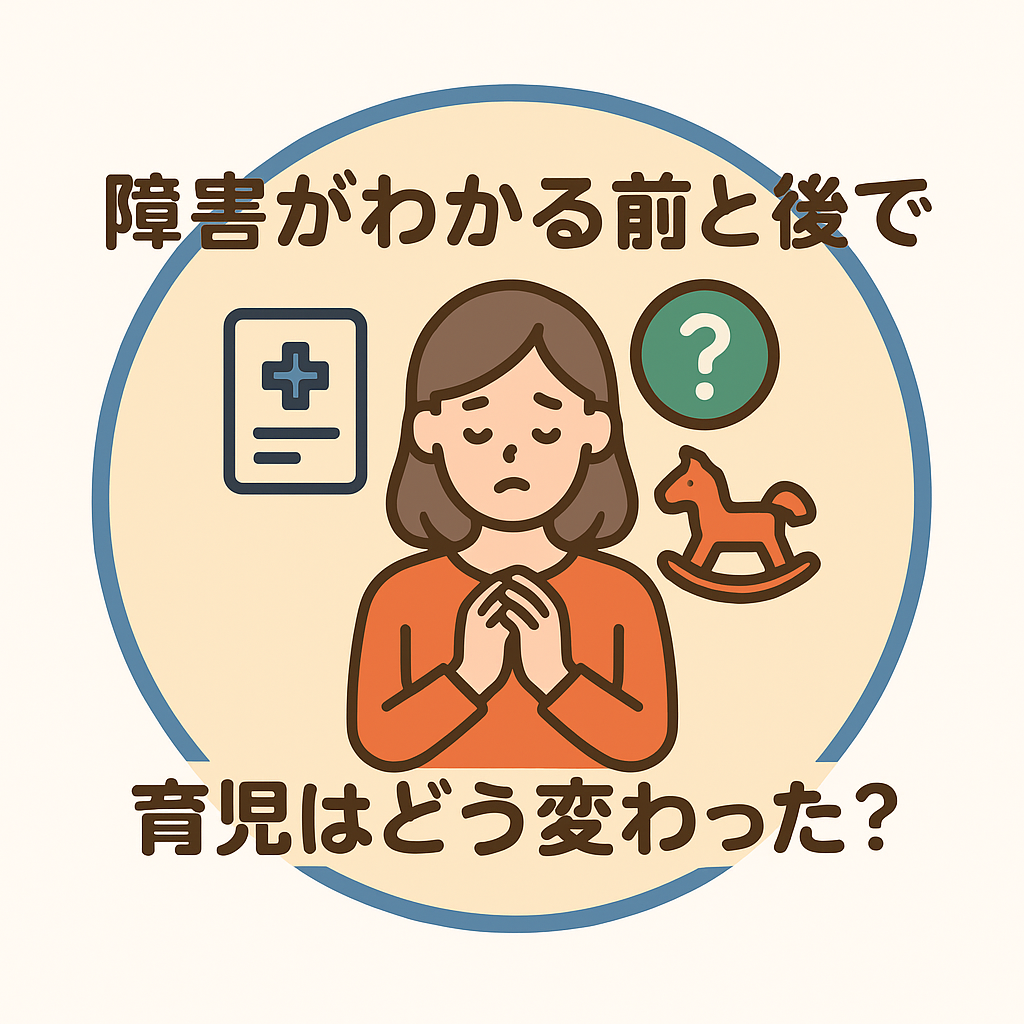
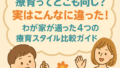
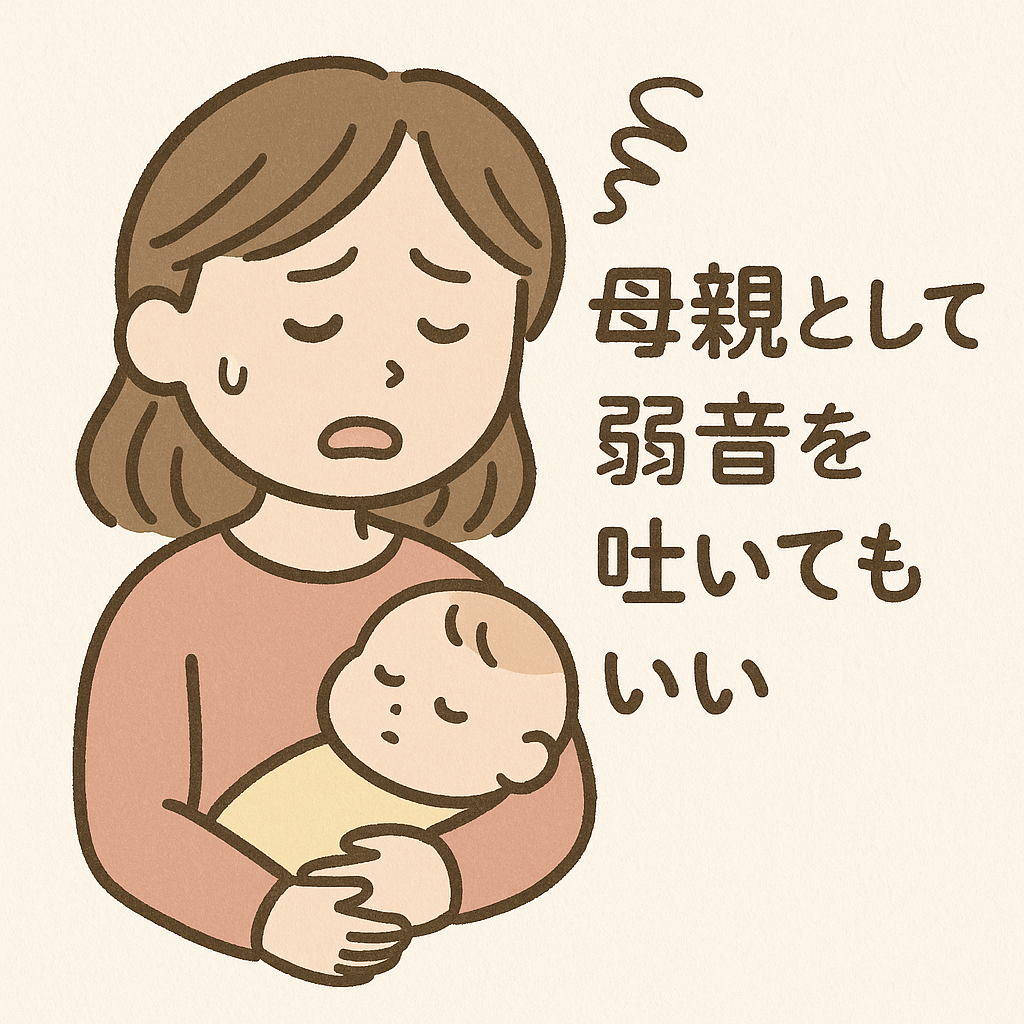
コメント